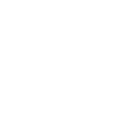
now loading...
caption
過ぎ去った分かれ道
真っ暗な闇の中で、周囲を照らす光の玉が宙に浮かぶ。
「やれやれ……どこまで落ちたんだ?」
光に照らされ、闇の中にシルヴァ・ラドクリフの姿が浮かび上がる。
「シルヴァ……無事だったのね」
その光に引かれるように、魔法戦士エリクシルライム、そしてエリクシルローズが近づいてきた。
シルヴァとエリクシルナイツは、先ほどまで古代遺跡の仲で激闘を繰り広げていた。
シルヴァが古代の魔法に関する遺物を手に入れようとしているという情報をキャッチしたエリクシルナイツが、彼を捕らえるために襲撃をしかけたのだった。
その戦いの際、遺跡の床が崩落し、三人とも地下へと落下してしまったのだった。
足下には水が流れており、どうやらここは水路になっているようだった。
「ここから登るのは……無理そうですわね」
穴が空いた床は、遙か上方でわずかな光を漏らしている。
ジャンプで到底届く高さではない。
崩落の瞬間、三人はそれぞれ魔法を使い、落下の衝撃を和らげたのだが、それがなければ体は粉々に砕けていただろう。それぐらいの高さを落ちたのだった。
シルヴァはエリクシルナイツの二人を見ながら言う。
「脱出するまで、一時休戦といかないか? ここで争うのはさすがに不毛だろう」
シルヴァの言葉に、ライムとローズは一度視線を交わした後、首を縦に振った。
「そうね。まずは脱出が先決だわ」
ライムが言うと、シルヴァは唇の端を上げた。
「それじゃ、久々にチーム結成といこうじゃないか」
冗談めかして言うシルヴァに、ライムもローズも眉間にしわを寄せる。
「……あくまで脱出までの間ですわよ。その後はあなたを捕まえますから」
ローズがトゲのある口調で言うと、シルヴァは肩を竦めた。
「でも、どうやって脱出すればいいのかしら?」
ライムも光の魔法を使い、周囲の状況を確認する。
石造りの水路となっており、壁には苔がびっしりと生え、滑ってとても登れそうにない。
「とりあえず、進んでみるしかないだろう」
シルヴァは水が流れてくる方向に顔を向ける。
この水がどこから流れてきているのかは不明だが、外の水源とつながっている可能性は高い。脱出を考えるのならばそちらに向かうのがセオリーだった。
「では、行きましょうか」
こうして、三人は地下水路を脱出すべく、しばらくの間同道することとなった。
 先頭を歩くシルヴァが、振り向かないまま口を開く。
「なあ、キールの行方は少しはつかんでるのか?」
シルヴァの問いに、ローズが答える。
「残念ですが、どこにいるのかまだわかっていませんわ。時々姿を見せるのですか、毎回捕まえ損ねてしまいます」
それを聞いて、シルヴァが肩を揺らして笑った。
「逃げ足の速さは、親父譲りのようだな」
キールの父親、メッツァー・ハインケルは、魔法戦士との戦いでは、躊躇せず撤退を繰り返していた。
そもそも、戦闘力では魔法戦士が大きく上回っているのだ。正面から戦っても勝ち目はない。
そこでメッツァーは戦闘の際に快楽を与えるという方法で、魔法戦士を籠絡しようとしたのである。
もちろん、魔法戦士たちも一度や二度淫悦を覚えさせられたくらいで、メッツァーに屈したりはしない。
なので、メッツァーは魔法戦士の心が折れるまで、その作戦を敢行し続けたのである。
何度も何度も、襲撃と撤退を繰り返しながら。
「キールはあなたが保護していたのよね。あなたから見てどんな人だったの、キールは」
ライムの問いに、シルヴァは少し考えてから答える。
「そうだな……かわいそうな奴、かな」
「かわいそう……?」
「そりゃそうだろう。銀髪の魔王とクイーンティアナ。厄介な血筋を二つも受け継いでる上、並行世界の未来からやって来たっておまけ付きだ。産まれた時から世界中の標的にされてるみたいな奴だからな」
シルヴァの言葉に、ライムとローズの表情に陰が差す。
「……そうですわね。キールの生い立ちはあまりに過酷ですわ」
「でも、だからと言って、悪事を見逃すわけにはいかないけど……」
魔法戦士であるエリクシルナイツからしても、キールの存在は複雑なところがあった。
ロアの女王ティアナの息子であると同時に、銀髪の魔王メッツァーの血脈でもある。
敬愛する女王と、憎むべき宿敵の血。
血筋で判断すべきではないとわかってはいるが、どうしても受け継いだ光と影をキールに見てしまうのだった。
「かわいそうだと思ったから、キールを助けたの?」
ライムの問いに、シルヴァは首を横に振る。
「いや……それだけなら、わざわざ手を差し伸べたりしないさ。こっちが余計なトラブルに巻き込まれかねないからな」
「では、どうしてですか?」
シルヴァの内心が気になり、ローズは深く聞き出したいと考えていた。
「まあ、一つは単純にメッツァーの息子だから、かな。あいつの子供見捨てるっていうのは、どうにも夢見が悪そうだしな」
どこか誤魔化すような口調でシルヴァはそう言った。
「他にも理由が?」
ライムが問うと、シルヴァは頭をかきながら答える。
「利用価値がないわけではなかった。クイーンティアナ、メッツァーの血縁、未来の情報……使い道は本当にいくらでもある」
「そうでしょうね……」
ローズが渋い顔で頷く。
シルヴァが言ったことこそが、キールの狙われる理由だった。
「だが、まあ、やはり一番の理由は、面白そうだったから、かな。あいつをあそこで終わらせるよりは、これから先、この世界でどんな役割を果たすのか。その行く末を見てみたくなってね」
随分と適当な理由だとエリクシルナイツは思った。
だが、シルヴァらしいとも思った。
「やっぱり、あいつはメッツァーの息子だよ。普通じゃない何かをもってると思わずにはいられないのさ。そういう奴を味方にしておいて損はない」
そう言って、シルヴァは小さく笑った。
やがて、水路の先にわずかな光が見えてきた。
「お、どうやら出口のようだぞ」
シルヴァが言い、エリクシルナイツも安堵の息を吐いた。
「よかった……どうやら脱出出来そうね」
ライムの気が緩んだその時だった。
目の前で水がいきなり盛り上がった。
「!?」
ライムは反射的に身構えるが、反応が一瞬遅れ、水の中から伸びてきた触手に全身を絡みつかれた。
「こ、これは!?」
焦りの声を上げるライムに、ローズが慌てて武器を構えて走る。
「ライム!」
触手を切断しようと剣を振り上げたが、それよりも早く、ライムは触手に引っ張られて水中に引きずり込まれた。
「……!」
水路の床に穴が開いていたらしく、ライムはその中へと引き込まれていく。
(こんな深い穴があるなんて……!)
ライムは頭を冷静に働かせつつ、触手の主が何者か確かめるべく、魔法の光で水中を照らす。
ライムを捕らえていたのは、全身から触手を生やした巨大な魚だった。全長は目測で4メートル以上はある。
(魚……!? 魔物の一種のようね……!)
水路の穴の奥は想像以上に広く、ちょっとした地下湖になっていた。巨大魚が充分泳ぎ回れる広さである。
(ここはこいつの巣……!? この中に獲物を引きずり込んで捕食してるってわけね!)
もちろん大人しく餌になるつもりなどない。
ライムは魔力を高めると、触手を引き剥がそうとする。
しかし、触手は想像以上に強靱で、まるで歯が立たなかった。
(どうなってるの……!? ただの魔物じゃない……!?)
相手は並ではないと認識を改めてライムは、先ほどよりも強く魔力を集中する。
そして、爆発的に魔力を膨張させると、全身に絡みつく触手を吹き飛ばした。
(やった……! とりあえず逃げないと……!)
水中は巨大魚のテリトリーである。不利な場所でわざわざ戦う必要はない。
ライムは自分が引き込まれた穴に向かって泳ごうとするが、獲物を逃すまいと、巨大魚が高速で迫ってきた。
巨大魚の牙を、ライムは間一髪で身をかわす。
(くっ……水中だと速さでこの魚には到底かなわないわね……! 戦うしかないか……!)
ライムは剣を引き抜くと、魔力を高めながら巨大魚と相対する。
双剣を合体させ、一本の武器にすると、ライムはそれを回転させ始めた。その回転により水中に渦が生まれ、その渦に巻き込まれた巨大魚の動きが鈍くなる。
その隙を狙い、ライムは渾身の一撃を叩き込んだ。
腹部を貫かれ、身悶えする巨大魚の周囲が赤く染まっていく。
(よし、倒した!)
勝利を確信したライムは、急いで水面へと浮上していく。
だが、その足を何かがつかんだ。
(!?)
振り向くと、そこには再び触手を伸ばした巨大魚がいた。
(そ、そんな、どうして!?)
水の朱色は拡散したのかすでに薄くなっており、その向こうに見える巨大魚の傷は、すでに塞がりかけていた。
巨大魚は頭を下に向けると、水深へと潜っていく。
大技で魔力を消耗したライムは抵抗出来ず、そのまま引きずり込まれていく。
(い、いけない、このままじゃ……!)
すでに呼吸が限界で、息苦しさで体が痺れてきている。
今襲われたらひとたまりもない。
水底まで潜った巨大魚は、触手を振って、ライムの体を近くに引き寄せる。
そして、そのまま大きな口を開けて噛みつこうとした。
(ただでやられたりはしない……!)
ライムは残った魔力をかき集め、迫る巨大魚の眼前で魔法の光を灯した。
次の瞬間、巨大魚は身をよじってライムから遠ざかった。
閉ざされた暗黒の水中に生息していた巨大魚は、ライムの読み通り光に弱かったのだ。
しかし、ライムはすでに限界だった。
(も、もう、水面まで泳ぐ力が……)
酸欠で意識が遠ざかっていく。
これが最期なのか――そんな思いが頭によぎった、その時だった。
柔らかな感触が唇に辺り、空気が口の中に滑り込んでくる。生存本能がそれを肺に取り込み、消えかけていたライムの意識が再び色づいた。
魔法の薄明かりの中、ライムの目に映ったのは、シルヴァの顔であった。
それでライムは理解する。
シルヴァが口移しで空気を与えてくれているのだ。
(シルヴァ……)
かつて何度も味わった、唇の感触。
ライムは半ば無意識に、シルヴァの背に手を回した――。
「げほっ、ごほっ!」
水上に出てきたライムは、飲んでいた水を吐く。
「ライム! 大丈夫ですか!?」
青ざめた顔のローズが、ライムの背中をさすった。
「だ、大丈夫……ありがとう、ローズ」
溺死寸前だったライムは、血の気の失せた顔で、それでもローズに向かって微笑んだ。
「やれやれ……まさかあんな化け物が棲んでいたとはな」
ライムを連れて浮上したシルヴァは、水路の床に開いていた穴を見ながら鼻を鳴らす。
「あ、あの魚は……一体?」
ライムの問いに、シルヴァは手に持っていた半透明の球を見せた。
「俺がこの遺跡で探していた古代の魔法が封じ込められていた宝玉だ。水中の台座に安置されていた。あの魚はこれの魔力で進化したのだろうな」
そう言って、シルヴァは宝玉を無造作に砕く。
「こんな危ないものは要らん」
シルヴァは宝玉の破片を投げ捨てると、ライムに向き直る。
「一つ貸しだな、亜梨子」
微笑を浮かべて言うシルヴァに、ライムは頬を染めて視線を逸らした。
地下水路を脱出したシルヴァとエリクシルナイツは、太陽の光を浴びて、ようやく気持ちが落ち着いていた。
「フ……とんだ大冒険だったな」
シルヴァはエリクシルナイツの方に振り向く。
「さて、さすがに疲れたし、俺は帰らせてもらうよ」
そう言うシルヴァに対し、どうすべきかライムもローズも迷いを見せていた。
「ライム、このままシルヴァを見逃すのは……」
「ええ、でも……」
ライムの命を救われたばかりでは、戦意も湧いてこない。それに、疲労した状態で戦っても、勝てるかどうか微妙だった。
そんな二人を見ながら、シルヴァは薄く笑う。
「お互いやめておこう。今日はもう戦う気分じゃない」
そう言ってシルヴァが手を上げると、物陰から何人もの武装した兵士たちが姿を見せた。
「お迎えに上がりました、シルヴァ様」
巨大な鎌を持ったメイドが、シルヴァに向かって恭しく頭を下げる。シルヴァの副官であるフィエナだった。
「アルケゼスト……!」
シルヴァの組織、アルケゼストの構成員たちが、いつの間にかこの場を取り囲んでいた。
シルヴァはエリクシルナイツに背中を向ける。
「帰投するぞ。無駄足だった」
それはアルケゼストの総裁であるシルヴァの、ここでこれ以上戦闘を行わないという意思表示、実質的な命令であった。
構成員たちはそれに従い、次々に姿を消す。
フィエナはエリクシルナイツに頭を下げた後、シルヴァとともに転移魔法で消え去ったのだった。
後に残されたライムとローズは、力の抜けた息を吐く。
「また……逃がしてしまいましたわね」
「うん……」
頷くライムは、自身の左手の薬指をじっと見つめる。そこにはかつて、シルヴァに与えられた指輪がはまっていた。
服従の魔力が込められた指輪が。
ライムは思う。
自分が誓ったシルヴァへの忠誠は、指輪の魔力のためだったのか。もしも、あの指輪が普通の指輪だったとしても、あの誓いは――。
「亜梨子さん」
ローズに声をかけられ、ライムの思考は打ち切られる。
心配そうに見ているローズに、ライムは笑顔を向けた。
「大丈夫、樹さん。私はもう、迷わないから」
ロアの将軍、クリザリッド・マサークレ率いる軍勢によって、アルケゼストが壊滅したという報告が届けられるのは、これよりしばらく後のことになる。
先頭を歩くシルヴァが、振り向かないまま口を開く。
「なあ、キールの行方は少しはつかんでるのか?」
シルヴァの問いに、ローズが答える。
「残念ですが、どこにいるのかまだわかっていませんわ。時々姿を見せるのですか、毎回捕まえ損ねてしまいます」
それを聞いて、シルヴァが肩を揺らして笑った。
「逃げ足の速さは、親父譲りのようだな」
キールの父親、メッツァー・ハインケルは、魔法戦士との戦いでは、躊躇せず撤退を繰り返していた。
そもそも、戦闘力では魔法戦士が大きく上回っているのだ。正面から戦っても勝ち目はない。
そこでメッツァーは戦闘の際に快楽を与えるという方法で、魔法戦士を籠絡しようとしたのである。
もちろん、魔法戦士たちも一度や二度淫悦を覚えさせられたくらいで、メッツァーに屈したりはしない。
なので、メッツァーは魔法戦士の心が折れるまで、その作戦を敢行し続けたのである。
何度も何度も、襲撃と撤退を繰り返しながら。
「キールはあなたが保護していたのよね。あなたから見てどんな人だったの、キールは」
ライムの問いに、シルヴァは少し考えてから答える。
「そうだな……かわいそうな奴、かな」
「かわいそう……?」
「そりゃそうだろう。銀髪の魔王とクイーンティアナ。厄介な血筋を二つも受け継いでる上、並行世界の未来からやって来たっておまけ付きだ。産まれた時から世界中の標的にされてるみたいな奴だからな」
シルヴァの言葉に、ライムとローズの表情に陰が差す。
「……そうですわね。キールの生い立ちはあまりに過酷ですわ」
「でも、だからと言って、悪事を見逃すわけにはいかないけど……」
魔法戦士であるエリクシルナイツからしても、キールの存在は複雑なところがあった。
ロアの女王ティアナの息子であると同時に、銀髪の魔王メッツァーの血脈でもある。
敬愛する女王と、憎むべき宿敵の血。
血筋で判断すべきではないとわかってはいるが、どうしても受け継いだ光と影をキールに見てしまうのだった。
「かわいそうだと思ったから、キールを助けたの?」
ライムの問いに、シルヴァは首を横に振る。
「いや……それだけなら、わざわざ手を差し伸べたりしないさ。こっちが余計なトラブルに巻き込まれかねないからな」
「では、どうしてですか?」
シルヴァの内心が気になり、ローズは深く聞き出したいと考えていた。
「まあ、一つは単純にメッツァーの息子だから、かな。あいつの子供見捨てるっていうのは、どうにも夢見が悪そうだしな」
どこか誤魔化すような口調でシルヴァはそう言った。
「他にも理由が?」
ライムが問うと、シルヴァは頭をかきながら答える。
「利用価値がないわけではなかった。クイーンティアナ、メッツァーの血縁、未来の情報……使い道は本当にいくらでもある」
「そうでしょうね……」
ローズが渋い顔で頷く。
シルヴァが言ったことこそが、キールの狙われる理由だった。
「だが、まあ、やはり一番の理由は、面白そうだったから、かな。あいつをあそこで終わらせるよりは、これから先、この世界でどんな役割を果たすのか。その行く末を見てみたくなってね」
随分と適当な理由だとエリクシルナイツは思った。
だが、シルヴァらしいとも思った。
「やっぱり、あいつはメッツァーの息子だよ。普通じゃない何かをもってると思わずにはいられないのさ。そういう奴を味方にしておいて損はない」
そう言って、シルヴァは小さく笑った。
やがて、水路の先にわずかな光が見えてきた。
「お、どうやら出口のようだぞ」
シルヴァが言い、エリクシルナイツも安堵の息を吐いた。
「よかった……どうやら脱出出来そうね」
ライムの気が緩んだその時だった。
目の前で水がいきなり盛り上がった。
「!?」
ライムは反射的に身構えるが、反応が一瞬遅れ、水の中から伸びてきた触手に全身を絡みつかれた。
「こ、これは!?」
焦りの声を上げるライムに、ローズが慌てて武器を構えて走る。
「ライム!」
触手を切断しようと剣を振り上げたが、それよりも早く、ライムは触手に引っ張られて水中に引きずり込まれた。
「……!」
水路の床に穴が開いていたらしく、ライムはその中へと引き込まれていく。
(こんな深い穴があるなんて……!)
ライムは頭を冷静に働かせつつ、触手の主が何者か確かめるべく、魔法の光で水中を照らす。
ライムを捕らえていたのは、全身から触手を生やした巨大な魚だった。全長は目測で4メートル以上はある。
(魚……!? 魔物の一種のようね……!)
水路の穴の奥は想像以上に広く、ちょっとした地下湖になっていた。巨大魚が充分泳ぎ回れる広さである。
(ここはこいつの巣……!? この中に獲物を引きずり込んで捕食してるってわけね!)
もちろん大人しく餌になるつもりなどない。
ライムは魔力を高めると、触手を引き剥がそうとする。
しかし、触手は想像以上に強靱で、まるで歯が立たなかった。
(どうなってるの……!? ただの魔物じゃない……!?)
相手は並ではないと認識を改めてライムは、先ほどよりも強く魔力を集中する。
そして、爆発的に魔力を膨張させると、全身に絡みつく触手を吹き飛ばした。
(やった……! とりあえず逃げないと……!)
水中は巨大魚のテリトリーである。不利な場所でわざわざ戦う必要はない。
ライムは自分が引き込まれた穴に向かって泳ごうとするが、獲物を逃すまいと、巨大魚が高速で迫ってきた。
巨大魚の牙を、ライムは間一髪で身をかわす。
(くっ……水中だと速さでこの魚には到底かなわないわね……! 戦うしかないか……!)
ライムは剣を引き抜くと、魔力を高めながら巨大魚と相対する。
双剣を合体させ、一本の武器にすると、ライムはそれを回転させ始めた。その回転により水中に渦が生まれ、その渦に巻き込まれた巨大魚の動きが鈍くなる。
その隙を狙い、ライムは渾身の一撃を叩き込んだ。
腹部を貫かれ、身悶えする巨大魚の周囲が赤く染まっていく。
(よし、倒した!)
勝利を確信したライムは、急いで水面へと浮上していく。
だが、その足を何かがつかんだ。
(!?)
振り向くと、そこには再び触手を伸ばした巨大魚がいた。
(そ、そんな、どうして!?)
水の朱色は拡散したのかすでに薄くなっており、その向こうに見える巨大魚の傷は、すでに塞がりかけていた。
巨大魚は頭を下に向けると、水深へと潜っていく。
大技で魔力を消耗したライムは抵抗出来ず、そのまま引きずり込まれていく。
(い、いけない、このままじゃ……!)
すでに呼吸が限界で、息苦しさで体が痺れてきている。
今襲われたらひとたまりもない。
水底まで潜った巨大魚は、触手を振って、ライムの体を近くに引き寄せる。
そして、そのまま大きな口を開けて噛みつこうとした。
(ただでやられたりはしない……!)
ライムは残った魔力をかき集め、迫る巨大魚の眼前で魔法の光を灯した。
次の瞬間、巨大魚は身をよじってライムから遠ざかった。
閉ざされた暗黒の水中に生息していた巨大魚は、ライムの読み通り光に弱かったのだ。
しかし、ライムはすでに限界だった。
(も、もう、水面まで泳ぐ力が……)
酸欠で意識が遠ざかっていく。
これが最期なのか――そんな思いが頭によぎった、その時だった。
柔らかな感触が唇に辺り、空気が口の中に滑り込んでくる。生存本能がそれを肺に取り込み、消えかけていたライムの意識が再び色づいた。
魔法の薄明かりの中、ライムの目に映ったのは、シルヴァの顔であった。
それでライムは理解する。
シルヴァが口移しで空気を与えてくれているのだ。
(シルヴァ……)
かつて何度も味わった、唇の感触。
ライムは半ば無意識に、シルヴァの背に手を回した――。
「げほっ、ごほっ!」
水上に出てきたライムは、飲んでいた水を吐く。
「ライム! 大丈夫ですか!?」
青ざめた顔のローズが、ライムの背中をさすった。
「だ、大丈夫……ありがとう、ローズ」
溺死寸前だったライムは、血の気の失せた顔で、それでもローズに向かって微笑んだ。
「やれやれ……まさかあんな化け物が棲んでいたとはな」
ライムを連れて浮上したシルヴァは、水路の床に開いていた穴を見ながら鼻を鳴らす。
「あ、あの魚は……一体?」
ライムの問いに、シルヴァは手に持っていた半透明の球を見せた。
「俺がこの遺跡で探していた古代の魔法が封じ込められていた宝玉だ。水中の台座に安置されていた。あの魚はこれの魔力で進化したのだろうな」
そう言って、シルヴァは宝玉を無造作に砕く。
「こんな危ないものは要らん」
シルヴァは宝玉の破片を投げ捨てると、ライムに向き直る。
「一つ貸しだな、亜梨子」
微笑を浮かべて言うシルヴァに、ライムは頬を染めて視線を逸らした。
地下水路を脱出したシルヴァとエリクシルナイツは、太陽の光を浴びて、ようやく気持ちが落ち着いていた。
「フ……とんだ大冒険だったな」
シルヴァはエリクシルナイツの方に振り向く。
「さて、さすがに疲れたし、俺は帰らせてもらうよ」
そう言うシルヴァに対し、どうすべきかライムもローズも迷いを見せていた。
「ライム、このままシルヴァを見逃すのは……」
「ええ、でも……」
ライムの命を救われたばかりでは、戦意も湧いてこない。それに、疲労した状態で戦っても、勝てるかどうか微妙だった。
そんな二人を見ながら、シルヴァは薄く笑う。
「お互いやめておこう。今日はもう戦う気分じゃない」
そう言ってシルヴァが手を上げると、物陰から何人もの武装した兵士たちが姿を見せた。
「お迎えに上がりました、シルヴァ様」
巨大な鎌を持ったメイドが、シルヴァに向かって恭しく頭を下げる。シルヴァの副官であるフィエナだった。
「アルケゼスト……!」
シルヴァの組織、アルケゼストの構成員たちが、いつの間にかこの場を取り囲んでいた。
シルヴァはエリクシルナイツに背中を向ける。
「帰投するぞ。無駄足だった」
それはアルケゼストの総裁であるシルヴァの、ここでこれ以上戦闘を行わないという意思表示、実質的な命令であった。
構成員たちはそれに従い、次々に姿を消す。
フィエナはエリクシルナイツに頭を下げた後、シルヴァとともに転移魔法で消え去ったのだった。
後に残されたライムとローズは、力の抜けた息を吐く。
「また……逃がしてしまいましたわね」
「うん……」
頷くライムは、自身の左手の薬指をじっと見つめる。そこにはかつて、シルヴァに与えられた指輪がはまっていた。
服従の魔力が込められた指輪が。
ライムは思う。
自分が誓ったシルヴァへの忠誠は、指輪の魔力のためだったのか。もしも、あの指輪が普通の指輪だったとしても、あの誓いは――。
「亜梨子さん」
ローズに声をかけられ、ライムの思考は打ち切られる。
心配そうに見ているローズに、ライムは笑顔を向けた。
「大丈夫、樹さん。私はもう、迷わないから」
ロアの将軍、クリザリッド・マサークレ率いる軍勢によって、アルケゼストが壊滅したという報告が届けられるのは、これよりしばらく後のことになる。
 先頭を歩くシルヴァが、振り向かないまま口を開く。
「なあ、キールの行方は少しはつかんでるのか?」
シルヴァの問いに、ローズが答える。
「残念ですが、どこにいるのかまだわかっていませんわ。時々姿を見せるのですか、毎回捕まえ損ねてしまいます」
それを聞いて、シルヴァが肩を揺らして笑った。
「逃げ足の速さは、親父譲りのようだな」
キールの父親、メッツァー・ハインケルは、魔法戦士との戦いでは、躊躇せず撤退を繰り返していた。
そもそも、戦闘力では魔法戦士が大きく上回っているのだ。正面から戦っても勝ち目はない。
そこでメッツァーは戦闘の際に快楽を与えるという方法で、魔法戦士を籠絡しようとしたのである。
もちろん、魔法戦士たちも一度や二度淫悦を覚えさせられたくらいで、メッツァーに屈したりはしない。
なので、メッツァーは魔法戦士の心が折れるまで、その作戦を敢行し続けたのである。
何度も何度も、襲撃と撤退を繰り返しながら。
「キールはあなたが保護していたのよね。あなたから見てどんな人だったの、キールは」
ライムの問いに、シルヴァは少し考えてから答える。
「そうだな……かわいそうな奴、かな」
「かわいそう……?」
「そりゃそうだろう。銀髪の魔王とクイーンティアナ。厄介な血筋を二つも受け継いでる上、並行世界の未来からやって来たっておまけ付きだ。産まれた時から世界中の標的にされてるみたいな奴だからな」
シルヴァの言葉に、ライムとローズの表情に陰が差す。
「……そうですわね。キールの生い立ちはあまりに過酷ですわ」
「でも、だからと言って、悪事を見逃すわけにはいかないけど……」
魔法戦士であるエリクシルナイツからしても、キールの存在は複雑なところがあった。
ロアの女王ティアナの息子であると同時に、銀髪の魔王メッツァーの血脈でもある。
敬愛する女王と、憎むべき宿敵の血。
血筋で判断すべきではないとわかってはいるが、どうしても受け継いだ光と影をキールに見てしまうのだった。
「かわいそうだと思ったから、キールを助けたの?」
ライムの問いに、シルヴァは首を横に振る。
「いや……それだけなら、わざわざ手を差し伸べたりしないさ。こっちが余計なトラブルに巻き込まれかねないからな」
「では、どうしてですか?」
シルヴァの内心が気になり、ローズは深く聞き出したいと考えていた。
「まあ、一つは単純にメッツァーの息子だから、かな。あいつの子供見捨てるっていうのは、どうにも夢見が悪そうだしな」
どこか誤魔化すような口調でシルヴァはそう言った。
「他にも理由が?」
ライムが問うと、シルヴァは頭をかきながら答える。
「利用価値がないわけではなかった。クイーンティアナ、メッツァーの血縁、未来の情報……使い道は本当にいくらでもある」
「そうでしょうね……」
ローズが渋い顔で頷く。
シルヴァが言ったことこそが、キールの狙われる理由だった。
「だが、まあ、やはり一番の理由は、面白そうだったから、かな。あいつをあそこで終わらせるよりは、これから先、この世界でどんな役割を果たすのか。その行く末を見てみたくなってね」
随分と適当な理由だとエリクシルナイツは思った。
だが、シルヴァらしいとも思った。
「やっぱり、あいつはメッツァーの息子だよ。普通じゃない何かをもってると思わずにはいられないのさ。そういう奴を味方にしておいて損はない」
そう言って、シルヴァは小さく笑った。
やがて、水路の先にわずかな光が見えてきた。
「お、どうやら出口のようだぞ」
シルヴァが言い、エリクシルナイツも安堵の息を吐いた。
「よかった……どうやら脱出出来そうね」
ライムの気が緩んだその時だった。
目の前で水がいきなり盛り上がった。
「!?」
ライムは反射的に身構えるが、反応が一瞬遅れ、水の中から伸びてきた触手に全身を絡みつかれた。
「こ、これは!?」
焦りの声を上げるライムに、ローズが慌てて武器を構えて走る。
「ライム!」
触手を切断しようと剣を振り上げたが、それよりも早く、ライムは触手に引っ張られて水中に引きずり込まれた。
「……!」
水路の床に穴が開いていたらしく、ライムはその中へと引き込まれていく。
(こんな深い穴があるなんて……!)
ライムは頭を冷静に働かせつつ、触手の主が何者か確かめるべく、魔法の光で水中を照らす。
ライムを捕らえていたのは、全身から触手を生やした巨大な魚だった。全長は目測で4メートル以上はある。
(魚……!? 魔物の一種のようね……!)
水路の穴の奥は想像以上に広く、ちょっとした地下湖になっていた。巨大魚が充分泳ぎ回れる広さである。
(ここはこいつの巣……!? この中に獲物を引きずり込んで捕食してるってわけね!)
もちろん大人しく餌になるつもりなどない。
ライムは魔力を高めると、触手を引き剥がそうとする。
しかし、触手は想像以上に強靱で、まるで歯が立たなかった。
(どうなってるの……!? ただの魔物じゃない……!?)
相手は並ではないと認識を改めてライムは、先ほどよりも強く魔力を集中する。
そして、爆発的に魔力を膨張させると、全身に絡みつく触手を吹き飛ばした。
(やった……! とりあえず逃げないと……!)
水中は巨大魚のテリトリーである。不利な場所でわざわざ戦う必要はない。
ライムは自分が引き込まれた穴に向かって泳ごうとするが、獲物を逃すまいと、巨大魚が高速で迫ってきた。
巨大魚の牙を、ライムは間一髪で身をかわす。
(くっ……水中だと速さでこの魚には到底かなわないわね……! 戦うしかないか……!)
ライムは剣を引き抜くと、魔力を高めながら巨大魚と相対する。
双剣を合体させ、一本の武器にすると、ライムはそれを回転させ始めた。その回転により水中に渦が生まれ、その渦に巻き込まれた巨大魚の動きが鈍くなる。
その隙を狙い、ライムは渾身の一撃を叩き込んだ。
腹部を貫かれ、身悶えする巨大魚の周囲が赤く染まっていく。
(よし、倒した!)
勝利を確信したライムは、急いで水面へと浮上していく。
だが、その足を何かがつかんだ。
(!?)
振り向くと、そこには再び触手を伸ばした巨大魚がいた。
(そ、そんな、どうして!?)
水の朱色は拡散したのかすでに薄くなっており、その向こうに見える巨大魚の傷は、すでに塞がりかけていた。
巨大魚は頭を下に向けると、水深へと潜っていく。
大技で魔力を消耗したライムは抵抗出来ず、そのまま引きずり込まれていく。
(い、いけない、このままじゃ……!)
すでに呼吸が限界で、息苦しさで体が痺れてきている。
今襲われたらひとたまりもない。
水底まで潜った巨大魚は、触手を振って、ライムの体を近くに引き寄せる。
そして、そのまま大きな口を開けて噛みつこうとした。
(ただでやられたりはしない……!)
ライムは残った魔力をかき集め、迫る巨大魚の眼前で魔法の光を灯した。
次の瞬間、巨大魚は身をよじってライムから遠ざかった。
閉ざされた暗黒の水中に生息していた巨大魚は、ライムの読み通り光に弱かったのだ。
しかし、ライムはすでに限界だった。
(も、もう、水面まで泳ぐ力が……)
酸欠で意識が遠ざかっていく。
これが最期なのか――そんな思いが頭によぎった、その時だった。
柔らかな感触が唇に辺り、空気が口の中に滑り込んでくる。生存本能がそれを肺に取り込み、消えかけていたライムの意識が再び色づいた。
魔法の薄明かりの中、ライムの目に映ったのは、シルヴァの顔であった。
それでライムは理解する。
シルヴァが口移しで空気を与えてくれているのだ。
(シルヴァ……)
かつて何度も味わった、唇の感触。
ライムは半ば無意識に、シルヴァの背に手を回した――。
「げほっ、ごほっ!」
水上に出てきたライムは、飲んでいた水を吐く。
「ライム! 大丈夫ですか!?」
青ざめた顔のローズが、ライムの背中をさすった。
「だ、大丈夫……ありがとう、ローズ」
溺死寸前だったライムは、血の気の失せた顔で、それでもローズに向かって微笑んだ。
「やれやれ……まさかあんな化け物が棲んでいたとはな」
ライムを連れて浮上したシルヴァは、水路の床に開いていた穴を見ながら鼻を鳴らす。
「あ、あの魚は……一体?」
ライムの問いに、シルヴァは手に持っていた半透明の球を見せた。
「俺がこの遺跡で探していた古代の魔法が封じ込められていた宝玉だ。水中の台座に安置されていた。あの魚はこれの魔力で進化したのだろうな」
そう言って、シルヴァは宝玉を無造作に砕く。
「こんな危ないものは要らん」
シルヴァは宝玉の破片を投げ捨てると、ライムに向き直る。
「一つ貸しだな、亜梨子」
微笑を浮かべて言うシルヴァに、ライムは頬を染めて視線を逸らした。
地下水路を脱出したシルヴァとエリクシルナイツは、太陽の光を浴びて、ようやく気持ちが落ち着いていた。
「フ……とんだ大冒険だったな」
シルヴァはエリクシルナイツの方に振り向く。
「さて、さすがに疲れたし、俺は帰らせてもらうよ」
そう言うシルヴァに対し、どうすべきかライムもローズも迷いを見せていた。
「ライム、このままシルヴァを見逃すのは……」
「ええ、でも……」
ライムの命を救われたばかりでは、戦意も湧いてこない。それに、疲労した状態で戦っても、勝てるかどうか微妙だった。
そんな二人を見ながら、シルヴァは薄く笑う。
「お互いやめておこう。今日はもう戦う気分じゃない」
そう言ってシルヴァが手を上げると、物陰から何人もの武装した兵士たちが姿を見せた。
「お迎えに上がりました、シルヴァ様」
巨大な鎌を持ったメイドが、シルヴァに向かって恭しく頭を下げる。シルヴァの副官であるフィエナだった。
「アルケゼスト……!」
シルヴァの組織、アルケゼストの構成員たちが、いつの間にかこの場を取り囲んでいた。
シルヴァはエリクシルナイツに背中を向ける。
「帰投するぞ。無駄足だった」
それはアルケゼストの総裁であるシルヴァの、ここでこれ以上戦闘を行わないという意思表示、実質的な命令であった。
構成員たちはそれに従い、次々に姿を消す。
フィエナはエリクシルナイツに頭を下げた後、シルヴァとともに転移魔法で消え去ったのだった。
後に残されたライムとローズは、力の抜けた息を吐く。
「また……逃がしてしまいましたわね」
「うん……」
頷くライムは、自身の左手の薬指をじっと見つめる。そこにはかつて、シルヴァに与えられた指輪がはまっていた。
服従の魔力が込められた指輪が。
ライムは思う。
自分が誓ったシルヴァへの忠誠は、指輪の魔力のためだったのか。もしも、あの指輪が普通の指輪だったとしても、あの誓いは――。
「亜梨子さん」
ローズに声をかけられ、ライムの思考は打ち切られる。
心配そうに見ているローズに、ライムは笑顔を向けた。
「大丈夫、樹さん。私はもう、迷わないから」
ロアの将軍、クリザリッド・マサークレ率いる軍勢によって、アルケゼストが壊滅したという報告が届けられるのは、これよりしばらく後のことになる。
先頭を歩くシルヴァが、振り向かないまま口を開く。
「なあ、キールの行方は少しはつかんでるのか?」
シルヴァの問いに、ローズが答える。
「残念ですが、どこにいるのかまだわかっていませんわ。時々姿を見せるのですか、毎回捕まえ損ねてしまいます」
それを聞いて、シルヴァが肩を揺らして笑った。
「逃げ足の速さは、親父譲りのようだな」
キールの父親、メッツァー・ハインケルは、魔法戦士との戦いでは、躊躇せず撤退を繰り返していた。
そもそも、戦闘力では魔法戦士が大きく上回っているのだ。正面から戦っても勝ち目はない。
そこでメッツァーは戦闘の際に快楽を与えるという方法で、魔法戦士を籠絡しようとしたのである。
もちろん、魔法戦士たちも一度や二度淫悦を覚えさせられたくらいで、メッツァーに屈したりはしない。
なので、メッツァーは魔法戦士の心が折れるまで、その作戦を敢行し続けたのである。
何度も何度も、襲撃と撤退を繰り返しながら。
「キールはあなたが保護していたのよね。あなたから見てどんな人だったの、キールは」
ライムの問いに、シルヴァは少し考えてから答える。
「そうだな……かわいそうな奴、かな」
「かわいそう……?」
「そりゃそうだろう。銀髪の魔王とクイーンティアナ。厄介な血筋を二つも受け継いでる上、並行世界の未来からやって来たっておまけ付きだ。産まれた時から世界中の標的にされてるみたいな奴だからな」
シルヴァの言葉に、ライムとローズの表情に陰が差す。
「……そうですわね。キールの生い立ちはあまりに過酷ですわ」
「でも、だからと言って、悪事を見逃すわけにはいかないけど……」
魔法戦士であるエリクシルナイツからしても、キールの存在は複雑なところがあった。
ロアの女王ティアナの息子であると同時に、銀髪の魔王メッツァーの血脈でもある。
敬愛する女王と、憎むべき宿敵の血。
血筋で判断すべきではないとわかってはいるが、どうしても受け継いだ光と影をキールに見てしまうのだった。
「かわいそうだと思ったから、キールを助けたの?」
ライムの問いに、シルヴァは首を横に振る。
「いや……それだけなら、わざわざ手を差し伸べたりしないさ。こっちが余計なトラブルに巻き込まれかねないからな」
「では、どうしてですか?」
シルヴァの内心が気になり、ローズは深く聞き出したいと考えていた。
「まあ、一つは単純にメッツァーの息子だから、かな。あいつの子供見捨てるっていうのは、どうにも夢見が悪そうだしな」
どこか誤魔化すような口調でシルヴァはそう言った。
「他にも理由が?」
ライムが問うと、シルヴァは頭をかきながら答える。
「利用価値がないわけではなかった。クイーンティアナ、メッツァーの血縁、未来の情報……使い道は本当にいくらでもある」
「そうでしょうね……」
ローズが渋い顔で頷く。
シルヴァが言ったことこそが、キールの狙われる理由だった。
「だが、まあ、やはり一番の理由は、面白そうだったから、かな。あいつをあそこで終わらせるよりは、これから先、この世界でどんな役割を果たすのか。その行く末を見てみたくなってね」
随分と適当な理由だとエリクシルナイツは思った。
だが、シルヴァらしいとも思った。
「やっぱり、あいつはメッツァーの息子だよ。普通じゃない何かをもってると思わずにはいられないのさ。そういう奴を味方にしておいて損はない」
そう言って、シルヴァは小さく笑った。
やがて、水路の先にわずかな光が見えてきた。
「お、どうやら出口のようだぞ」
シルヴァが言い、エリクシルナイツも安堵の息を吐いた。
「よかった……どうやら脱出出来そうね」
ライムの気が緩んだその時だった。
目の前で水がいきなり盛り上がった。
「!?」
ライムは反射的に身構えるが、反応が一瞬遅れ、水の中から伸びてきた触手に全身を絡みつかれた。
「こ、これは!?」
焦りの声を上げるライムに、ローズが慌てて武器を構えて走る。
「ライム!」
触手を切断しようと剣を振り上げたが、それよりも早く、ライムは触手に引っ張られて水中に引きずり込まれた。
「……!」
水路の床に穴が開いていたらしく、ライムはその中へと引き込まれていく。
(こんな深い穴があるなんて……!)
ライムは頭を冷静に働かせつつ、触手の主が何者か確かめるべく、魔法の光で水中を照らす。
ライムを捕らえていたのは、全身から触手を生やした巨大な魚だった。全長は目測で4メートル以上はある。
(魚……!? 魔物の一種のようね……!)
水路の穴の奥は想像以上に広く、ちょっとした地下湖になっていた。巨大魚が充分泳ぎ回れる広さである。
(ここはこいつの巣……!? この中に獲物を引きずり込んで捕食してるってわけね!)
もちろん大人しく餌になるつもりなどない。
ライムは魔力を高めると、触手を引き剥がそうとする。
しかし、触手は想像以上に強靱で、まるで歯が立たなかった。
(どうなってるの……!? ただの魔物じゃない……!?)
相手は並ではないと認識を改めてライムは、先ほどよりも強く魔力を集中する。
そして、爆発的に魔力を膨張させると、全身に絡みつく触手を吹き飛ばした。
(やった……! とりあえず逃げないと……!)
水中は巨大魚のテリトリーである。不利な場所でわざわざ戦う必要はない。
ライムは自分が引き込まれた穴に向かって泳ごうとするが、獲物を逃すまいと、巨大魚が高速で迫ってきた。
巨大魚の牙を、ライムは間一髪で身をかわす。
(くっ……水中だと速さでこの魚には到底かなわないわね……! 戦うしかないか……!)
ライムは剣を引き抜くと、魔力を高めながら巨大魚と相対する。
双剣を合体させ、一本の武器にすると、ライムはそれを回転させ始めた。その回転により水中に渦が生まれ、その渦に巻き込まれた巨大魚の動きが鈍くなる。
その隙を狙い、ライムは渾身の一撃を叩き込んだ。
腹部を貫かれ、身悶えする巨大魚の周囲が赤く染まっていく。
(よし、倒した!)
勝利を確信したライムは、急いで水面へと浮上していく。
だが、その足を何かがつかんだ。
(!?)
振り向くと、そこには再び触手を伸ばした巨大魚がいた。
(そ、そんな、どうして!?)
水の朱色は拡散したのかすでに薄くなっており、その向こうに見える巨大魚の傷は、すでに塞がりかけていた。
巨大魚は頭を下に向けると、水深へと潜っていく。
大技で魔力を消耗したライムは抵抗出来ず、そのまま引きずり込まれていく。
(い、いけない、このままじゃ……!)
すでに呼吸が限界で、息苦しさで体が痺れてきている。
今襲われたらひとたまりもない。
水底まで潜った巨大魚は、触手を振って、ライムの体を近くに引き寄せる。
そして、そのまま大きな口を開けて噛みつこうとした。
(ただでやられたりはしない……!)
ライムは残った魔力をかき集め、迫る巨大魚の眼前で魔法の光を灯した。
次の瞬間、巨大魚は身をよじってライムから遠ざかった。
閉ざされた暗黒の水中に生息していた巨大魚は、ライムの読み通り光に弱かったのだ。
しかし、ライムはすでに限界だった。
(も、もう、水面まで泳ぐ力が……)
酸欠で意識が遠ざかっていく。
これが最期なのか――そんな思いが頭によぎった、その時だった。
柔らかな感触が唇に辺り、空気が口の中に滑り込んでくる。生存本能がそれを肺に取り込み、消えかけていたライムの意識が再び色づいた。
魔法の薄明かりの中、ライムの目に映ったのは、シルヴァの顔であった。
それでライムは理解する。
シルヴァが口移しで空気を与えてくれているのだ。
(シルヴァ……)
かつて何度も味わった、唇の感触。
ライムは半ば無意識に、シルヴァの背に手を回した――。
「げほっ、ごほっ!」
水上に出てきたライムは、飲んでいた水を吐く。
「ライム! 大丈夫ですか!?」
青ざめた顔のローズが、ライムの背中をさすった。
「だ、大丈夫……ありがとう、ローズ」
溺死寸前だったライムは、血の気の失せた顔で、それでもローズに向かって微笑んだ。
「やれやれ……まさかあんな化け物が棲んでいたとはな」
ライムを連れて浮上したシルヴァは、水路の床に開いていた穴を見ながら鼻を鳴らす。
「あ、あの魚は……一体?」
ライムの問いに、シルヴァは手に持っていた半透明の球を見せた。
「俺がこの遺跡で探していた古代の魔法が封じ込められていた宝玉だ。水中の台座に安置されていた。あの魚はこれの魔力で進化したのだろうな」
そう言って、シルヴァは宝玉を無造作に砕く。
「こんな危ないものは要らん」
シルヴァは宝玉の破片を投げ捨てると、ライムに向き直る。
「一つ貸しだな、亜梨子」
微笑を浮かべて言うシルヴァに、ライムは頬を染めて視線を逸らした。
地下水路を脱出したシルヴァとエリクシルナイツは、太陽の光を浴びて、ようやく気持ちが落ち着いていた。
「フ……とんだ大冒険だったな」
シルヴァはエリクシルナイツの方に振り向く。
「さて、さすがに疲れたし、俺は帰らせてもらうよ」
そう言うシルヴァに対し、どうすべきかライムもローズも迷いを見せていた。
「ライム、このままシルヴァを見逃すのは……」
「ええ、でも……」
ライムの命を救われたばかりでは、戦意も湧いてこない。それに、疲労した状態で戦っても、勝てるかどうか微妙だった。
そんな二人を見ながら、シルヴァは薄く笑う。
「お互いやめておこう。今日はもう戦う気分じゃない」
そう言ってシルヴァが手を上げると、物陰から何人もの武装した兵士たちが姿を見せた。
「お迎えに上がりました、シルヴァ様」
巨大な鎌を持ったメイドが、シルヴァに向かって恭しく頭を下げる。シルヴァの副官であるフィエナだった。
「アルケゼスト……!」
シルヴァの組織、アルケゼストの構成員たちが、いつの間にかこの場を取り囲んでいた。
シルヴァはエリクシルナイツに背中を向ける。
「帰投するぞ。無駄足だった」
それはアルケゼストの総裁であるシルヴァの、ここでこれ以上戦闘を行わないという意思表示、実質的な命令であった。
構成員たちはそれに従い、次々に姿を消す。
フィエナはエリクシルナイツに頭を下げた後、シルヴァとともに転移魔法で消え去ったのだった。
後に残されたライムとローズは、力の抜けた息を吐く。
「また……逃がしてしまいましたわね」
「うん……」
頷くライムは、自身の左手の薬指をじっと見つめる。そこにはかつて、シルヴァに与えられた指輪がはまっていた。
服従の魔力が込められた指輪が。
ライムは思う。
自分が誓ったシルヴァへの忠誠は、指輪の魔力のためだったのか。もしも、あの指輪が普通の指輪だったとしても、あの誓いは――。
「亜梨子さん」
ローズに声をかけられ、ライムの思考は打ち切られる。
心配そうに見ているローズに、ライムは笑顔を向けた。
「大丈夫、樹さん。私はもう、迷わないから」
ロアの将軍、クリザリッド・マサークレ率いる軍勢によって、アルケゼストが壊滅したという報告が届けられるのは、これよりしばらく後のことになる。

