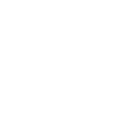
now loading...
caption
光が生むもの
首都から少し外れた工業地帯。
工場が並ぶ区画の中に、大きく開けた空き地がある。
空き地の中にはプレハブ小屋が一つだけ建っており、入り口のそばには施工主と施工業者、そして工期が記された縦長の黒板が置かれている。
一見すればこれから何らかの工場でも建つかのような体裁が整えられている――が、この場を訪れた二人の女性は、それが偽装であることを知っていた。
プレハブ小屋に入った二人は、使われた形跡のない軍手や作業服を横目に、台車の置かれた一角を目指す。
セメント袋が一袋だけ乗せられた台車を押すと、その下には正方形に細い溝が掘られた床があった。木製のその床の正方形の中には、丁度指を入れられそうなくぼみがある。
女性の一人がそのくぼみに指をかけ、正方形の板を持ち上げる。
その下には、地下へと続く階段があった。
二人の女性は階段を降りて地下へと進んでいく。
暗い階段を降りきると、センサーに反応したのかライトが光を放ち、人工的な通路がその姿を見せた。
通路は鉄とセメントで固められており、建築物の体を為している。
秘匿されている地下施設――その中を二人の女性は進む。
そして、通路の終点でドアにぶつかった。
ドアの脇には暗証番号を入れるためのテンキーと、指紋を照合するためのスキャンディスプレイ、網膜認証のためのレンズがある。
それらのロックがすべて解除されていることを確認し、二人の女性はドアを開く。その瞬間、肌を刺すような冷気が溢れ出てきた。
二人はゆっくりと部屋の中に足を進める。
室内には低温で唸る箱形の大きな機械がいくつも並んでいる。
人の背ほどもあるその機械の横を進んでいくと、部屋の奥で無数に並んだモニターの前に座っている背中があった。
 「ファルケ……!」
女性の一人が出した声に、その人物は座ったまま椅子を回転させて振り向く。
それは、全身鎧のようなものを着込んだ人間だった。口元だけが唯一露出しており、少しだけ伸びている髭で鎧の中身が男性だとわかった。
強化スキン――そう名付けられたアーマーを着込んでいる男は、二人の女性を見て唇を笑みの形に歪めた。
「ほう、もうお出ましか。さすがに早いな、シンフォニックナイツ」
シンフォニックナイツと呼ばれた二人の女性は、警戒の目でじっとファルケを見る。
シンフォニックナイツは地上世界の平和を守るため、科学と魔力を融合させた技術で悪と戦う「魔法戦士」である。
シンフォニックリリーは百合瀬財団の総帥である百合瀬莉々奈が、そしてシンフォニックシュガーは変身システムの開発者である甘樹菜々芭が変身した姿であった。
リリーが剣を構えてファルケに言う。
「ここで何をしているのですか、ファルケ!」
ファルケは薄く笑うと、椅子に深く座り直す。
「ちょっと調べ物をね。なかなかいい設備が揃ってるな、ここは」
世間話でもするように喋るファルケを、シュガーが睨む。
「ここの研究員たちはどこにいるのですか?」
「全員奥の部屋で転がっているよ。可哀想に、随分疲れていたみたいだな。みんなぐっすりお休みだ」
おどけたように言うファルケに、リリーは剣の切っ先を突きつけた。
「ここに侵入した目的は何ですか、ファルケ」
リリーの問いに、ファルケは背後のモニターに目をやりながら答える。
「ま、純粋な興味かな。政府主導の魔法研究機関が、どこまで進んでいるのか知っておきたくてね」
この地下施設は政府の作った魔法の研究所であった。
ファルケの襲撃を受けた研究所からのSOSを受け取った政府が、財界の大物でもあり魔法戦士でもあるシンフォニックナイツに助けを求めたのだった。
「……それで、何か面白いものは見つかりましたか?」
シュガーの問いに、ファルケは皮肉めいた笑みを浮かべて肩を竦める。
「まあ、面白くはないが、ある意味では面白いものがね」
そう言ってファルケは小馬鹿にしたように鼻を鳴らすと、コンソールを操作してモニターにデータを映し出す。
複数のモニターに並べられたデータを見て、シンフォニックナイツは思わず目を見開いた。
「こ、これは……M3システムの開発概要……!?」
自分が開発したシステムを解析したらしきデータ類を見て、シュガーは驚きに固まる。
「これだけじゃない」
そう言って、ファルケがキーを叩くと、今度は別のデータが表示された。
「……!」
モニターに次々と映されるデータは、魔法戦士についての研究データだった。
主に変身システムを中心に解析を進めているらしく、どれも不完全ではあるもののかなり踏み込んで研究されていた。
「ククク……どうやら政府は魔法戦士の力を管理することをまだ諦めてはいないようだな」
ファルケの小馬鹿にしたような笑いに、リリーは歯軋りをする。
以前、魔法戦士を政府が管理しようという計画が持ち上がった。政権内部にいる魔法戦士に協力的な一派によって、その計画は危ういところで阻止された。
しかし、魔法戦士の力を利用しようという勢力が潰えたわけではない。それはレムティアナイツが狙われたエニグマの一件で明らかになった。
魔法災害はまだ連日発生しており、魔法戦士を守ろうとしてくれている与党は支持率的に苦戦している。
魔法災害に対抗するための力を得るということは、今の世情においては政治的に大きな意味を持つ。
地上世界で最強の魔力を持つ存在、魔法戦士の力を研究することは、ある意味当然であると言えるかも知れない。
そしてそれは、魔法戦士たちが何より恐れていることだった。
「魔法戦士の力を……兵器として扱うつもりですか……!」
リリーは俯きながら唇を噛む。
魔法を汎用化することによって、兵装として実用化する。そのための研究開発は世界中の国で行われている。
魔法技術はまだどの先進国でも発展途上であり、もし魔法戦士の力を武力化出来れば、諸外国に対して圧倒的なアドバンテージになり得る。その機会を逃すほど、政府関係者は甘くなかった。
現在の与党は魔法戦士に好意的だが、野党や官僚はそうではない。魔法戦士の力を利用しようとする権力者は各界にいくらでもいる。
さらに、一部のマスコミや言論人も強大な魔力を操る魔法戦士を危険視する論陣を張っている。まるで大量破壊兵器のような扱われ方だった。
そのせいか、魔法戦士寄りの与党は支持率で苦戦しており、次回の総選挙での政権交代もかなり現実味を帯びている。
莉々奈は財界の大物ではあるが、魔法戦士という立場上、特定の政党に肩入れするのは難しかった。
「お前たち魔法戦士も、ようやく世間に受け入れられたと思ったんだがな」
そう言ってファルケは肩を揺らして笑う。
「例えどう思われようと、私たちは魔法戦士の使命を果たすだけです……!」
そう言ってリリーはファルケを鋭く睨む。
リリーの視線を受けながら、ファルケは不意に表情を改めた。
「……急だと思わないか? 魔法戦士に対する風向きが変わったのは」
「……何が言いたいんですか?」
シュガーが探るような目をファルケに向ける。
ファルケはコンソールを操作し、モニターに地上波のニュース番組を映す。
その番組では魔法災害の被害について伝えながら、魔法戦士の批判派と擁護派が意見を戦わせていた。
「魔法戦士の擁護派と批判派の対立。お前たちに関する報道の姿勢は大体この構図だ」
魔法戦士に対しては必ずしも批判一辺倒というわけではない。その活動内容を称賛し、擁護する人たちもいる。
魔法戦士たちにとってはありがたい味方と言える。
だが、ファルケは底意地の悪い笑みを浮かべた。
「上手いやり方だ。一方の意見だけを流さず、それに反する意見も報道する。何より、擁護派の人選が絶妙だ」
「どういうことですか……?」
ファルケの言わんとしていることがわからず、リリーは怪訝な顔をする。
ファルケは薄い笑みを浮かべながら言った。
「擁護派の論陣にいる連中は、理由は色々だがどいつもこいつもネット上では嫌われ者でね。インターネットの世界ではこいつらの裏に魔法戦士がいて、好意的な意見を流させてる、と言う陰謀論がまことしやかに語られている」
「な!?」
初めて聞いた話にシンフォニックナイツは驚く。
ファルケは忍び笑いをこぼしながら続ける。
「人間というものは単純だよ。冷静に考えれば荒唐無稽に思える陰謀論でも、悪だと決めつけた相手が対象となると途端に真実に見えてくる。嫌悪している相手を悪だと補強してくれる材料が増えれば、それだけ自分が正義なのだと思い込めるからな。正義は凡庸な人々にとって実に手軽で中毒性の高い『娯楽』なんだよ」
そう言って嘲笑するファルケに、シンフォニックナイツたちは剣呑な目で向ける。
「おっと、そんな目で見ないでくれよ。君たちの正義はそんな安っぽいものとは違う。さすがにそれくらい俺だって心得ているさ。問題は、その娯楽を意図的に提供している誰かがいるんじゃないかってことだ」
ファルケの言葉に、シュガーの表情が動く。
「何者かがメディアを利用して情報操作をしていると……?」
ファルケは唇の端を歪めて頷きを返した。
「そう考えた方が色々と筋が通ることが多くてね」
リリーとシュガーはお互いに顔を見合わせる。
ファルケの言葉をそのまま受け取る愚は犯せないが、否定するだけの材料はない。
それに、二人も最近の世論の急激な傾きに不自然さを感じていたのだ。
それを何者かが裏で操っているとするならば――。
リリーとシュガーはファルケに向き直る。
「情報操作の裏にいる人物……それに心当たりがあるのですか?」
リリーの問いに、ファルケは肩を竦めた。
「残念ながら。だが、手がかりならある」
そう言って、ファルケは再びコンソールを操作する。
ニュース番組の映像が消え、モニターに新たに映し出されたのはファルケの強化スキンの設計図だった。
「この強化スキンの設計図……何者かがデプレダという魔界の組織に流出させたのは知っているな?」
ファルケの言葉にリリーとシュガーは頷く。
この強化スキンを元に、魔物が地上世界でも力を損なわない装備、凶魔スキンが生み出された。
「誰がデータを盗んだのか、俺も気になってね。色々と調べていたんだが……どうも雲行きが怪しくてね」
「どういうことですか……?」
怪訝な顔をするシュガーに、ファルケは肩を竦める。
「この開発データはいざという時のために俺がネットに隠しておいたものだ。魔界の連中が到底探し出せるものじゃない。見つけ出すのは地上世界の人間の協力が必要になるだろう」
「こっちの世界にデプレダの協力者が?」
魔界の組織であるデプレダは、地上で自由に活動出来ない制限があるため、地上の人間を使って工作活動をしていた。
国際教導学園を一時乗っ取った池岡政次という男も、政府の官僚でありながらデプレダの協力者だった。
「俺はその協力者についても突き止めた。あのデータにアクセス出来るのは世界でも一握りのハッカーだけだ。探すのはそう難しくなかったよ。だが、そこからがどうも妙な話でな……」
ファルケは椅子に座り直し、前傾姿勢になりながらシンフォニックナイツをじっと見つめた。
「しばらくそのハッカーの周囲を観察していたが、魔界の気配がまるでない。それどころか、そいつは裏で政府ともつながっているような奴だった」
「政府と……!?」
リリーが驚いたように目を見開く。
「そうだ。そしてそれだけじゃない。そのハッカーは政府を通じて、ロアの人間とも接触しているような形跡があった」
「なっ……!?」
ファルケの言わんとしているところを察し、シュガーが吃驚する。
「わかったようだな、シンフォニックシュガー。強化スキンの情報をデプレダに流したのは、ロアの人間の可能性もあるってことだ」
「そ、そんなバカな! そんなことあり得ません!」
思わず大声を上げたリリーに、ファルケは鼻を鳴らす。
「現実を見ろ。レムティアナイツの一件で裏にいたのは王宮内部の人間だったじゃないか。デプレダとつながっている奴がいたっておかしくはないだろう。そんな奴にとって、女王に近い地上の魔法戦士は邪魔な存在のはずだ」
ファルケの嘲るような物言いに、リリーは奥歯を噛む。
確かにファルケの言う通り、今は王宮内の人間でも無条件に信用できる状況ではなかった。
ファルケは背もたれに体重を預け、小馬鹿にしたような笑みをこぼす。
「敵対している魔界はもとより、今後ロアは地上世界でも良くも悪くも大きな存在になるだろう。魔物に対抗するため、魔法技術の進歩のため、あらゆる事象でロアの存在が欠かせなくなる。恐らく世界の中心となっていくだろう。そして光が強くなれば、当然影も濃くなる」
「…………」
シンフォニックナイツはファルケに何も言い返せない。ファルケの分析は正しく、そしてシンフォニックナイツも同じように考えていたからだった。
「権力欲しさに蠢き出すのは一人や二人じゃないだろう。そんな臣下どもを抑えるには、ティアナ女王は力不足だったんじゃないか?」
ファルケの言葉に、リリーが鋭い視線を向ける。
「クイーン・ティアナは懸命に国を治めています。ロアも、地上世界も平和であるために、身を捧げて働いていらっしゃるのです……!」
リリーの声に怒りにも似た迫力が滲む。
そんなリリーを探るように見ながら、ファルケは言う。
「治世の才はあっても、王となるには若すぎたんじゃないか? 前女王のグロリアに引退を撤回してもらって、戻ってきてもらった方が……」
「やめてください!」
リリーがたまりかねたように叫ぶ。
その過剰とも言える反応に、ファルケは喉の奥で小さく唸った。
「……まあ、話はここまでにしようか。あまり長居しているわけにもいかないからな。俺とシルヴァはロアの軍隊にも追われているみたいなんでね。また会おう、シンフォニックナイツ」
それだけ言うと、ファルケは転移魔法によってその場から姿を消した。
「しまった……! あらかじめ転移魔法の準備を……!」
ファルケを取り逃がし、シュガーは悔しそうに唇を噛む。
「…………」
リリーは武器を納めると、拳を握りしめて俯く。
そんなリリーにシュガーが寄り添った。
「……状況はよくありません。ですが、いつか平和が来ると信じて戦い続けましょう。私たちにできるのはそれだけなんですから」
優しく励ましてくれるシュガーに、リリーは微笑を向けた後、決意とともに表情を改めた。
「うん……私たちは負けるわけにはいかない……クイーンティアナのため……そして、もういないグロリア様のためにも……!」
「ファルケ……!」
女性の一人が出した声に、その人物は座ったまま椅子を回転させて振り向く。
それは、全身鎧のようなものを着込んだ人間だった。口元だけが唯一露出しており、少しだけ伸びている髭で鎧の中身が男性だとわかった。
強化スキン――そう名付けられたアーマーを着込んでいる男は、二人の女性を見て唇を笑みの形に歪めた。
「ほう、もうお出ましか。さすがに早いな、シンフォニックナイツ」
シンフォニックナイツと呼ばれた二人の女性は、警戒の目でじっとファルケを見る。
シンフォニックナイツは地上世界の平和を守るため、科学と魔力を融合させた技術で悪と戦う「魔法戦士」である。
シンフォニックリリーは百合瀬財団の総帥である百合瀬莉々奈が、そしてシンフォニックシュガーは変身システムの開発者である甘樹菜々芭が変身した姿であった。
リリーが剣を構えてファルケに言う。
「ここで何をしているのですか、ファルケ!」
ファルケは薄く笑うと、椅子に深く座り直す。
「ちょっと調べ物をね。なかなかいい設備が揃ってるな、ここは」
世間話でもするように喋るファルケを、シュガーが睨む。
「ここの研究員たちはどこにいるのですか?」
「全員奥の部屋で転がっているよ。可哀想に、随分疲れていたみたいだな。みんなぐっすりお休みだ」
おどけたように言うファルケに、リリーは剣の切っ先を突きつけた。
「ここに侵入した目的は何ですか、ファルケ」
リリーの問いに、ファルケは背後のモニターに目をやりながら答える。
「ま、純粋な興味かな。政府主導の魔法研究機関が、どこまで進んでいるのか知っておきたくてね」
この地下施設は政府の作った魔法の研究所であった。
ファルケの襲撃を受けた研究所からのSOSを受け取った政府が、財界の大物でもあり魔法戦士でもあるシンフォニックナイツに助けを求めたのだった。
「……それで、何か面白いものは見つかりましたか?」
シュガーの問いに、ファルケは皮肉めいた笑みを浮かべて肩を竦める。
「まあ、面白くはないが、ある意味では面白いものがね」
そう言ってファルケは小馬鹿にしたように鼻を鳴らすと、コンソールを操作してモニターにデータを映し出す。
複数のモニターに並べられたデータを見て、シンフォニックナイツは思わず目を見開いた。
「こ、これは……M3システムの開発概要……!?」
自分が開発したシステムを解析したらしきデータ類を見て、シュガーは驚きに固まる。
「これだけじゃない」
そう言って、ファルケがキーを叩くと、今度は別のデータが表示された。
「……!」
モニターに次々と映されるデータは、魔法戦士についての研究データだった。
主に変身システムを中心に解析を進めているらしく、どれも不完全ではあるもののかなり踏み込んで研究されていた。
「ククク……どうやら政府は魔法戦士の力を管理することをまだ諦めてはいないようだな」
ファルケの小馬鹿にしたような笑いに、リリーは歯軋りをする。
以前、魔法戦士を政府が管理しようという計画が持ち上がった。政権内部にいる魔法戦士に協力的な一派によって、その計画は危ういところで阻止された。
しかし、魔法戦士の力を利用しようという勢力が潰えたわけではない。それはレムティアナイツが狙われたエニグマの一件で明らかになった。
魔法災害はまだ連日発生しており、魔法戦士を守ろうとしてくれている与党は支持率的に苦戦している。
魔法災害に対抗するための力を得るということは、今の世情においては政治的に大きな意味を持つ。
地上世界で最強の魔力を持つ存在、魔法戦士の力を研究することは、ある意味当然であると言えるかも知れない。
そしてそれは、魔法戦士たちが何より恐れていることだった。
「魔法戦士の力を……兵器として扱うつもりですか……!」
リリーは俯きながら唇を噛む。
魔法を汎用化することによって、兵装として実用化する。そのための研究開発は世界中の国で行われている。
魔法技術はまだどの先進国でも発展途上であり、もし魔法戦士の力を武力化出来れば、諸外国に対して圧倒的なアドバンテージになり得る。その機会を逃すほど、政府関係者は甘くなかった。
現在の与党は魔法戦士に好意的だが、野党や官僚はそうではない。魔法戦士の力を利用しようとする権力者は各界にいくらでもいる。
さらに、一部のマスコミや言論人も強大な魔力を操る魔法戦士を危険視する論陣を張っている。まるで大量破壊兵器のような扱われ方だった。
そのせいか、魔法戦士寄りの与党は支持率で苦戦しており、次回の総選挙での政権交代もかなり現実味を帯びている。
莉々奈は財界の大物ではあるが、魔法戦士という立場上、特定の政党に肩入れするのは難しかった。
「お前たち魔法戦士も、ようやく世間に受け入れられたと思ったんだがな」
そう言ってファルケは肩を揺らして笑う。
「例えどう思われようと、私たちは魔法戦士の使命を果たすだけです……!」
そう言ってリリーはファルケを鋭く睨む。
リリーの視線を受けながら、ファルケは不意に表情を改めた。
「……急だと思わないか? 魔法戦士に対する風向きが変わったのは」
「……何が言いたいんですか?」
シュガーが探るような目をファルケに向ける。
ファルケはコンソールを操作し、モニターに地上波のニュース番組を映す。
その番組では魔法災害の被害について伝えながら、魔法戦士の批判派と擁護派が意見を戦わせていた。
「魔法戦士の擁護派と批判派の対立。お前たちに関する報道の姿勢は大体この構図だ」
魔法戦士に対しては必ずしも批判一辺倒というわけではない。その活動内容を称賛し、擁護する人たちもいる。
魔法戦士たちにとってはありがたい味方と言える。
だが、ファルケは底意地の悪い笑みを浮かべた。
「上手いやり方だ。一方の意見だけを流さず、それに反する意見も報道する。何より、擁護派の人選が絶妙だ」
「どういうことですか……?」
ファルケの言わんとしていることがわからず、リリーは怪訝な顔をする。
ファルケは薄い笑みを浮かべながら言った。
「擁護派の論陣にいる連中は、理由は色々だがどいつもこいつもネット上では嫌われ者でね。インターネットの世界ではこいつらの裏に魔法戦士がいて、好意的な意見を流させてる、と言う陰謀論がまことしやかに語られている」
「な!?」
初めて聞いた話にシンフォニックナイツは驚く。
ファルケは忍び笑いをこぼしながら続ける。
「人間というものは単純だよ。冷静に考えれば荒唐無稽に思える陰謀論でも、悪だと決めつけた相手が対象となると途端に真実に見えてくる。嫌悪している相手を悪だと補強してくれる材料が増えれば、それだけ自分が正義なのだと思い込めるからな。正義は凡庸な人々にとって実に手軽で中毒性の高い『娯楽』なんだよ」
そう言って嘲笑するファルケに、シンフォニックナイツたちは剣呑な目で向ける。
「おっと、そんな目で見ないでくれよ。君たちの正義はそんな安っぽいものとは違う。さすがにそれくらい俺だって心得ているさ。問題は、その娯楽を意図的に提供している誰かがいるんじゃないかってことだ」
ファルケの言葉に、シュガーの表情が動く。
「何者かがメディアを利用して情報操作をしていると……?」
ファルケは唇の端を歪めて頷きを返した。
「そう考えた方が色々と筋が通ることが多くてね」
リリーとシュガーはお互いに顔を見合わせる。
ファルケの言葉をそのまま受け取る愚は犯せないが、否定するだけの材料はない。
それに、二人も最近の世論の急激な傾きに不自然さを感じていたのだ。
それを何者かが裏で操っているとするならば――。
リリーとシュガーはファルケに向き直る。
「情報操作の裏にいる人物……それに心当たりがあるのですか?」
リリーの問いに、ファルケは肩を竦めた。
「残念ながら。だが、手がかりならある」
そう言って、ファルケは再びコンソールを操作する。
ニュース番組の映像が消え、モニターに新たに映し出されたのはファルケの強化スキンの設計図だった。
「この強化スキンの設計図……何者かがデプレダという魔界の組織に流出させたのは知っているな?」
ファルケの言葉にリリーとシュガーは頷く。
この強化スキンを元に、魔物が地上世界でも力を損なわない装備、凶魔スキンが生み出された。
「誰がデータを盗んだのか、俺も気になってね。色々と調べていたんだが……どうも雲行きが怪しくてね」
「どういうことですか……?」
怪訝な顔をするシュガーに、ファルケは肩を竦める。
「この開発データはいざという時のために俺がネットに隠しておいたものだ。魔界の連中が到底探し出せるものじゃない。見つけ出すのは地上世界の人間の協力が必要になるだろう」
「こっちの世界にデプレダの協力者が?」
魔界の組織であるデプレダは、地上で自由に活動出来ない制限があるため、地上の人間を使って工作活動をしていた。
国際教導学園を一時乗っ取った池岡政次という男も、政府の官僚でありながらデプレダの協力者だった。
「俺はその協力者についても突き止めた。あのデータにアクセス出来るのは世界でも一握りのハッカーだけだ。探すのはそう難しくなかったよ。だが、そこからがどうも妙な話でな……」
ファルケは椅子に座り直し、前傾姿勢になりながらシンフォニックナイツをじっと見つめた。
「しばらくそのハッカーの周囲を観察していたが、魔界の気配がまるでない。それどころか、そいつは裏で政府ともつながっているような奴だった」
「政府と……!?」
リリーが驚いたように目を見開く。
「そうだ。そしてそれだけじゃない。そのハッカーは政府を通じて、ロアの人間とも接触しているような形跡があった」
「なっ……!?」
ファルケの言わんとしているところを察し、シュガーが吃驚する。
「わかったようだな、シンフォニックシュガー。強化スキンの情報をデプレダに流したのは、ロアの人間の可能性もあるってことだ」
「そ、そんなバカな! そんなことあり得ません!」
思わず大声を上げたリリーに、ファルケは鼻を鳴らす。
「現実を見ろ。レムティアナイツの一件で裏にいたのは王宮内部の人間だったじゃないか。デプレダとつながっている奴がいたっておかしくはないだろう。そんな奴にとって、女王に近い地上の魔法戦士は邪魔な存在のはずだ」
ファルケの嘲るような物言いに、リリーは奥歯を噛む。
確かにファルケの言う通り、今は王宮内の人間でも無条件に信用できる状況ではなかった。
ファルケは背もたれに体重を預け、小馬鹿にしたような笑みをこぼす。
「敵対している魔界はもとより、今後ロアは地上世界でも良くも悪くも大きな存在になるだろう。魔物に対抗するため、魔法技術の進歩のため、あらゆる事象でロアの存在が欠かせなくなる。恐らく世界の中心となっていくだろう。そして光が強くなれば、当然影も濃くなる」
「…………」
シンフォニックナイツはファルケに何も言い返せない。ファルケの分析は正しく、そしてシンフォニックナイツも同じように考えていたからだった。
「権力欲しさに蠢き出すのは一人や二人じゃないだろう。そんな臣下どもを抑えるには、ティアナ女王は力不足だったんじゃないか?」
ファルケの言葉に、リリーが鋭い視線を向ける。
「クイーン・ティアナは懸命に国を治めています。ロアも、地上世界も平和であるために、身を捧げて働いていらっしゃるのです……!」
リリーの声に怒りにも似た迫力が滲む。
そんなリリーを探るように見ながら、ファルケは言う。
「治世の才はあっても、王となるには若すぎたんじゃないか? 前女王のグロリアに引退を撤回してもらって、戻ってきてもらった方が……」
「やめてください!」
リリーがたまりかねたように叫ぶ。
その過剰とも言える反応に、ファルケは喉の奥で小さく唸った。
「……まあ、話はここまでにしようか。あまり長居しているわけにもいかないからな。俺とシルヴァはロアの軍隊にも追われているみたいなんでね。また会おう、シンフォニックナイツ」
それだけ言うと、ファルケは転移魔法によってその場から姿を消した。
「しまった……! あらかじめ転移魔法の準備を……!」
ファルケを取り逃がし、シュガーは悔しそうに唇を噛む。
「…………」
リリーは武器を納めると、拳を握りしめて俯く。
そんなリリーにシュガーが寄り添った。
「……状況はよくありません。ですが、いつか平和が来ると信じて戦い続けましょう。私たちにできるのはそれだけなんですから」
優しく励ましてくれるシュガーに、リリーは微笑を向けた後、決意とともに表情を改めた。
「うん……私たちは負けるわけにはいかない……クイーンティアナのため……そして、もういないグロリア様のためにも……!」
 「ファルケ……!」
女性の一人が出した声に、その人物は座ったまま椅子を回転させて振り向く。
それは、全身鎧のようなものを着込んだ人間だった。口元だけが唯一露出しており、少しだけ伸びている髭で鎧の中身が男性だとわかった。
強化スキン――そう名付けられたアーマーを着込んでいる男は、二人の女性を見て唇を笑みの形に歪めた。
「ほう、もうお出ましか。さすがに早いな、シンフォニックナイツ」
シンフォニックナイツと呼ばれた二人の女性は、警戒の目でじっとファルケを見る。
シンフォニックナイツは地上世界の平和を守るため、科学と魔力を融合させた技術で悪と戦う「魔法戦士」である。
シンフォニックリリーは百合瀬財団の総帥である百合瀬莉々奈が、そしてシンフォニックシュガーは変身システムの開発者である甘樹菜々芭が変身した姿であった。
リリーが剣を構えてファルケに言う。
「ここで何をしているのですか、ファルケ!」
ファルケは薄く笑うと、椅子に深く座り直す。
「ちょっと調べ物をね。なかなかいい設備が揃ってるな、ここは」
世間話でもするように喋るファルケを、シュガーが睨む。
「ここの研究員たちはどこにいるのですか?」
「全員奥の部屋で転がっているよ。可哀想に、随分疲れていたみたいだな。みんなぐっすりお休みだ」
おどけたように言うファルケに、リリーは剣の切っ先を突きつけた。
「ここに侵入した目的は何ですか、ファルケ」
リリーの問いに、ファルケは背後のモニターに目をやりながら答える。
「ま、純粋な興味かな。政府主導の魔法研究機関が、どこまで進んでいるのか知っておきたくてね」
この地下施設は政府の作った魔法の研究所であった。
ファルケの襲撃を受けた研究所からのSOSを受け取った政府が、財界の大物でもあり魔法戦士でもあるシンフォニックナイツに助けを求めたのだった。
「……それで、何か面白いものは見つかりましたか?」
シュガーの問いに、ファルケは皮肉めいた笑みを浮かべて肩を竦める。
「まあ、面白くはないが、ある意味では面白いものがね」
そう言ってファルケは小馬鹿にしたように鼻を鳴らすと、コンソールを操作してモニターにデータを映し出す。
複数のモニターに並べられたデータを見て、シンフォニックナイツは思わず目を見開いた。
「こ、これは……M3システムの開発概要……!?」
自分が開発したシステムを解析したらしきデータ類を見て、シュガーは驚きに固まる。
「これだけじゃない」
そう言って、ファルケがキーを叩くと、今度は別のデータが表示された。
「……!」
モニターに次々と映されるデータは、魔法戦士についての研究データだった。
主に変身システムを中心に解析を進めているらしく、どれも不完全ではあるもののかなり踏み込んで研究されていた。
「ククク……どうやら政府は魔法戦士の力を管理することをまだ諦めてはいないようだな」
ファルケの小馬鹿にしたような笑いに、リリーは歯軋りをする。
以前、魔法戦士を政府が管理しようという計画が持ち上がった。政権内部にいる魔法戦士に協力的な一派によって、その計画は危ういところで阻止された。
しかし、魔法戦士の力を利用しようという勢力が潰えたわけではない。それはレムティアナイツが狙われたエニグマの一件で明らかになった。
魔法災害はまだ連日発生しており、魔法戦士を守ろうとしてくれている与党は支持率的に苦戦している。
魔法災害に対抗するための力を得るということは、今の世情においては政治的に大きな意味を持つ。
地上世界で最強の魔力を持つ存在、魔法戦士の力を研究することは、ある意味当然であると言えるかも知れない。
そしてそれは、魔法戦士たちが何より恐れていることだった。
「魔法戦士の力を……兵器として扱うつもりですか……!」
リリーは俯きながら唇を噛む。
魔法を汎用化することによって、兵装として実用化する。そのための研究開発は世界中の国で行われている。
魔法技術はまだどの先進国でも発展途上であり、もし魔法戦士の力を武力化出来れば、諸外国に対して圧倒的なアドバンテージになり得る。その機会を逃すほど、政府関係者は甘くなかった。
現在の与党は魔法戦士に好意的だが、野党や官僚はそうではない。魔法戦士の力を利用しようとする権力者は各界にいくらでもいる。
さらに、一部のマスコミや言論人も強大な魔力を操る魔法戦士を危険視する論陣を張っている。まるで大量破壊兵器のような扱われ方だった。
そのせいか、魔法戦士寄りの与党は支持率で苦戦しており、次回の総選挙での政権交代もかなり現実味を帯びている。
莉々奈は財界の大物ではあるが、魔法戦士という立場上、特定の政党に肩入れするのは難しかった。
「お前たち魔法戦士も、ようやく世間に受け入れられたと思ったんだがな」
そう言ってファルケは肩を揺らして笑う。
「例えどう思われようと、私たちは魔法戦士の使命を果たすだけです……!」
そう言ってリリーはファルケを鋭く睨む。
リリーの視線を受けながら、ファルケは不意に表情を改めた。
「……急だと思わないか? 魔法戦士に対する風向きが変わったのは」
「……何が言いたいんですか?」
シュガーが探るような目をファルケに向ける。
ファルケはコンソールを操作し、モニターに地上波のニュース番組を映す。
その番組では魔法災害の被害について伝えながら、魔法戦士の批判派と擁護派が意見を戦わせていた。
「魔法戦士の擁護派と批判派の対立。お前たちに関する報道の姿勢は大体この構図だ」
魔法戦士に対しては必ずしも批判一辺倒というわけではない。その活動内容を称賛し、擁護する人たちもいる。
魔法戦士たちにとってはありがたい味方と言える。
だが、ファルケは底意地の悪い笑みを浮かべた。
「上手いやり方だ。一方の意見だけを流さず、それに反する意見も報道する。何より、擁護派の人選が絶妙だ」
「どういうことですか……?」
ファルケの言わんとしていることがわからず、リリーは怪訝な顔をする。
ファルケは薄い笑みを浮かべながら言った。
「擁護派の論陣にいる連中は、理由は色々だがどいつもこいつもネット上では嫌われ者でね。インターネットの世界ではこいつらの裏に魔法戦士がいて、好意的な意見を流させてる、と言う陰謀論がまことしやかに語られている」
「な!?」
初めて聞いた話にシンフォニックナイツは驚く。
ファルケは忍び笑いをこぼしながら続ける。
「人間というものは単純だよ。冷静に考えれば荒唐無稽に思える陰謀論でも、悪だと決めつけた相手が対象となると途端に真実に見えてくる。嫌悪している相手を悪だと補強してくれる材料が増えれば、それだけ自分が正義なのだと思い込めるからな。正義は凡庸な人々にとって実に手軽で中毒性の高い『娯楽』なんだよ」
そう言って嘲笑するファルケに、シンフォニックナイツたちは剣呑な目で向ける。
「おっと、そんな目で見ないでくれよ。君たちの正義はそんな安っぽいものとは違う。さすがにそれくらい俺だって心得ているさ。問題は、その娯楽を意図的に提供している誰かがいるんじゃないかってことだ」
ファルケの言葉に、シュガーの表情が動く。
「何者かがメディアを利用して情報操作をしていると……?」
ファルケは唇の端を歪めて頷きを返した。
「そう考えた方が色々と筋が通ることが多くてね」
リリーとシュガーはお互いに顔を見合わせる。
ファルケの言葉をそのまま受け取る愚は犯せないが、否定するだけの材料はない。
それに、二人も最近の世論の急激な傾きに不自然さを感じていたのだ。
それを何者かが裏で操っているとするならば――。
リリーとシュガーはファルケに向き直る。
「情報操作の裏にいる人物……それに心当たりがあるのですか?」
リリーの問いに、ファルケは肩を竦めた。
「残念ながら。だが、手がかりならある」
そう言って、ファルケは再びコンソールを操作する。
ニュース番組の映像が消え、モニターに新たに映し出されたのはファルケの強化スキンの設計図だった。
「この強化スキンの設計図……何者かがデプレダという魔界の組織に流出させたのは知っているな?」
ファルケの言葉にリリーとシュガーは頷く。
この強化スキンを元に、魔物が地上世界でも力を損なわない装備、凶魔スキンが生み出された。
「誰がデータを盗んだのか、俺も気になってね。色々と調べていたんだが……どうも雲行きが怪しくてね」
「どういうことですか……?」
怪訝な顔をするシュガーに、ファルケは肩を竦める。
「この開発データはいざという時のために俺がネットに隠しておいたものだ。魔界の連中が到底探し出せるものじゃない。見つけ出すのは地上世界の人間の協力が必要になるだろう」
「こっちの世界にデプレダの協力者が?」
魔界の組織であるデプレダは、地上で自由に活動出来ない制限があるため、地上の人間を使って工作活動をしていた。
国際教導学園を一時乗っ取った池岡政次という男も、政府の官僚でありながらデプレダの協力者だった。
「俺はその協力者についても突き止めた。あのデータにアクセス出来るのは世界でも一握りのハッカーだけだ。探すのはそう難しくなかったよ。だが、そこからがどうも妙な話でな……」
ファルケは椅子に座り直し、前傾姿勢になりながらシンフォニックナイツをじっと見つめた。
「しばらくそのハッカーの周囲を観察していたが、魔界の気配がまるでない。それどころか、そいつは裏で政府ともつながっているような奴だった」
「政府と……!?」
リリーが驚いたように目を見開く。
「そうだ。そしてそれだけじゃない。そのハッカーは政府を通じて、ロアの人間とも接触しているような形跡があった」
「なっ……!?」
ファルケの言わんとしているところを察し、シュガーが吃驚する。
「わかったようだな、シンフォニックシュガー。強化スキンの情報をデプレダに流したのは、ロアの人間の可能性もあるってことだ」
「そ、そんなバカな! そんなことあり得ません!」
思わず大声を上げたリリーに、ファルケは鼻を鳴らす。
「現実を見ろ。レムティアナイツの一件で裏にいたのは王宮内部の人間だったじゃないか。デプレダとつながっている奴がいたっておかしくはないだろう。そんな奴にとって、女王に近い地上の魔法戦士は邪魔な存在のはずだ」
ファルケの嘲るような物言いに、リリーは奥歯を噛む。
確かにファルケの言う通り、今は王宮内の人間でも無条件に信用できる状況ではなかった。
ファルケは背もたれに体重を預け、小馬鹿にしたような笑みをこぼす。
「敵対している魔界はもとより、今後ロアは地上世界でも良くも悪くも大きな存在になるだろう。魔物に対抗するため、魔法技術の進歩のため、あらゆる事象でロアの存在が欠かせなくなる。恐らく世界の中心となっていくだろう。そして光が強くなれば、当然影も濃くなる」
「…………」
シンフォニックナイツはファルケに何も言い返せない。ファルケの分析は正しく、そしてシンフォニックナイツも同じように考えていたからだった。
「権力欲しさに蠢き出すのは一人や二人じゃないだろう。そんな臣下どもを抑えるには、ティアナ女王は力不足だったんじゃないか?」
ファルケの言葉に、リリーが鋭い視線を向ける。
「クイーン・ティアナは懸命に国を治めています。ロアも、地上世界も平和であるために、身を捧げて働いていらっしゃるのです……!」
リリーの声に怒りにも似た迫力が滲む。
そんなリリーを探るように見ながら、ファルケは言う。
「治世の才はあっても、王となるには若すぎたんじゃないか? 前女王のグロリアに引退を撤回してもらって、戻ってきてもらった方が……」
「やめてください!」
リリーがたまりかねたように叫ぶ。
その過剰とも言える反応に、ファルケは喉の奥で小さく唸った。
「……まあ、話はここまでにしようか。あまり長居しているわけにもいかないからな。俺とシルヴァはロアの軍隊にも追われているみたいなんでね。また会おう、シンフォニックナイツ」
それだけ言うと、ファルケは転移魔法によってその場から姿を消した。
「しまった……! あらかじめ転移魔法の準備を……!」
ファルケを取り逃がし、シュガーは悔しそうに唇を噛む。
「…………」
リリーは武器を納めると、拳を握りしめて俯く。
そんなリリーにシュガーが寄り添った。
「……状況はよくありません。ですが、いつか平和が来ると信じて戦い続けましょう。私たちにできるのはそれだけなんですから」
優しく励ましてくれるシュガーに、リリーは微笑を向けた後、決意とともに表情を改めた。
「うん……私たちは負けるわけにはいかない……クイーンティアナのため……そして、もういないグロリア様のためにも……!」
「ファルケ……!」
女性の一人が出した声に、その人物は座ったまま椅子を回転させて振り向く。
それは、全身鎧のようなものを着込んだ人間だった。口元だけが唯一露出しており、少しだけ伸びている髭で鎧の中身が男性だとわかった。
強化スキン――そう名付けられたアーマーを着込んでいる男は、二人の女性を見て唇を笑みの形に歪めた。
「ほう、もうお出ましか。さすがに早いな、シンフォニックナイツ」
シンフォニックナイツと呼ばれた二人の女性は、警戒の目でじっとファルケを見る。
シンフォニックナイツは地上世界の平和を守るため、科学と魔力を融合させた技術で悪と戦う「魔法戦士」である。
シンフォニックリリーは百合瀬財団の総帥である百合瀬莉々奈が、そしてシンフォニックシュガーは変身システムの開発者である甘樹菜々芭が変身した姿であった。
リリーが剣を構えてファルケに言う。
「ここで何をしているのですか、ファルケ!」
ファルケは薄く笑うと、椅子に深く座り直す。
「ちょっと調べ物をね。なかなかいい設備が揃ってるな、ここは」
世間話でもするように喋るファルケを、シュガーが睨む。
「ここの研究員たちはどこにいるのですか?」
「全員奥の部屋で転がっているよ。可哀想に、随分疲れていたみたいだな。みんなぐっすりお休みだ」
おどけたように言うファルケに、リリーは剣の切っ先を突きつけた。
「ここに侵入した目的は何ですか、ファルケ」
リリーの問いに、ファルケは背後のモニターに目をやりながら答える。
「ま、純粋な興味かな。政府主導の魔法研究機関が、どこまで進んでいるのか知っておきたくてね」
この地下施設は政府の作った魔法の研究所であった。
ファルケの襲撃を受けた研究所からのSOSを受け取った政府が、財界の大物でもあり魔法戦士でもあるシンフォニックナイツに助けを求めたのだった。
「……それで、何か面白いものは見つかりましたか?」
シュガーの問いに、ファルケは皮肉めいた笑みを浮かべて肩を竦める。
「まあ、面白くはないが、ある意味では面白いものがね」
そう言ってファルケは小馬鹿にしたように鼻を鳴らすと、コンソールを操作してモニターにデータを映し出す。
複数のモニターに並べられたデータを見て、シンフォニックナイツは思わず目を見開いた。
「こ、これは……M3システムの開発概要……!?」
自分が開発したシステムを解析したらしきデータ類を見て、シュガーは驚きに固まる。
「これだけじゃない」
そう言って、ファルケがキーを叩くと、今度は別のデータが表示された。
「……!」
モニターに次々と映されるデータは、魔法戦士についての研究データだった。
主に変身システムを中心に解析を進めているらしく、どれも不完全ではあるもののかなり踏み込んで研究されていた。
「ククク……どうやら政府は魔法戦士の力を管理することをまだ諦めてはいないようだな」
ファルケの小馬鹿にしたような笑いに、リリーは歯軋りをする。
以前、魔法戦士を政府が管理しようという計画が持ち上がった。政権内部にいる魔法戦士に協力的な一派によって、その計画は危ういところで阻止された。
しかし、魔法戦士の力を利用しようという勢力が潰えたわけではない。それはレムティアナイツが狙われたエニグマの一件で明らかになった。
魔法災害はまだ連日発生しており、魔法戦士を守ろうとしてくれている与党は支持率的に苦戦している。
魔法災害に対抗するための力を得るということは、今の世情においては政治的に大きな意味を持つ。
地上世界で最強の魔力を持つ存在、魔法戦士の力を研究することは、ある意味当然であると言えるかも知れない。
そしてそれは、魔法戦士たちが何より恐れていることだった。
「魔法戦士の力を……兵器として扱うつもりですか……!」
リリーは俯きながら唇を噛む。
魔法を汎用化することによって、兵装として実用化する。そのための研究開発は世界中の国で行われている。
魔法技術はまだどの先進国でも発展途上であり、もし魔法戦士の力を武力化出来れば、諸外国に対して圧倒的なアドバンテージになり得る。その機会を逃すほど、政府関係者は甘くなかった。
現在の与党は魔法戦士に好意的だが、野党や官僚はそうではない。魔法戦士の力を利用しようとする権力者は各界にいくらでもいる。
さらに、一部のマスコミや言論人も強大な魔力を操る魔法戦士を危険視する論陣を張っている。まるで大量破壊兵器のような扱われ方だった。
そのせいか、魔法戦士寄りの与党は支持率で苦戦しており、次回の総選挙での政権交代もかなり現実味を帯びている。
莉々奈は財界の大物ではあるが、魔法戦士という立場上、特定の政党に肩入れするのは難しかった。
「お前たち魔法戦士も、ようやく世間に受け入れられたと思ったんだがな」
そう言ってファルケは肩を揺らして笑う。
「例えどう思われようと、私たちは魔法戦士の使命を果たすだけです……!」
そう言ってリリーはファルケを鋭く睨む。
リリーの視線を受けながら、ファルケは不意に表情を改めた。
「……急だと思わないか? 魔法戦士に対する風向きが変わったのは」
「……何が言いたいんですか?」
シュガーが探るような目をファルケに向ける。
ファルケはコンソールを操作し、モニターに地上波のニュース番組を映す。
その番組では魔法災害の被害について伝えながら、魔法戦士の批判派と擁護派が意見を戦わせていた。
「魔法戦士の擁護派と批判派の対立。お前たちに関する報道の姿勢は大体この構図だ」
魔法戦士に対しては必ずしも批判一辺倒というわけではない。その活動内容を称賛し、擁護する人たちもいる。
魔法戦士たちにとってはありがたい味方と言える。
だが、ファルケは底意地の悪い笑みを浮かべた。
「上手いやり方だ。一方の意見だけを流さず、それに反する意見も報道する。何より、擁護派の人選が絶妙だ」
「どういうことですか……?」
ファルケの言わんとしていることがわからず、リリーは怪訝な顔をする。
ファルケは薄い笑みを浮かべながら言った。
「擁護派の論陣にいる連中は、理由は色々だがどいつもこいつもネット上では嫌われ者でね。インターネットの世界ではこいつらの裏に魔法戦士がいて、好意的な意見を流させてる、と言う陰謀論がまことしやかに語られている」
「な!?」
初めて聞いた話にシンフォニックナイツは驚く。
ファルケは忍び笑いをこぼしながら続ける。
「人間というものは単純だよ。冷静に考えれば荒唐無稽に思える陰謀論でも、悪だと決めつけた相手が対象となると途端に真実に見えてくる。嫌悪している相手を悪だと補強してくれる材料が増えれば、それだけ自分が正義なのだと思い込めるからな。正義は凡庸な人々にとって実に手軽で中毒性の高い『娯楽』なんだよ」
そう言って嘲笑するファルケに、シンフォニックナイツたちは剣呑な目で向ける。
「おっと、そんな目で見ないでくれよ。君たちの正義はそんな安っぽいものとは違う。さすがにそれくらい俺だって心得ているさ。問題は、その娯楽を意図的に提供している誰かがいるんじゃないかってことだ」
ファルケの言葉に、シュガーの表情が動く。
「何者かがメディアを利用して情報操作をしていると……?」
ファルケは唇の端を歪めて頷きを返した。
「そう考えた方が色々と筋が通ることが多くてね」
リリーとシュガーはお互いに顔を見合わせる。
ファルケの言葉をそのまま受け取る愚は犯せないが、否定するだけの材料はない。
それに、二人も最近の世論の急激な傾きに不自然さを感じていたのだ。
それを何者かが裏で操っているとするならば――。
リリーとシュガーはファルケに向き直る。
「情報操作の裏にいる人物……それに心当たりがあるのですか?」
リリーの問いに、ファルケは肩を竦めた。
「残念ながら。だが、手がかりならある」
そう言って、ファルケは再びコンソールを操作する。
ニュース番組の映像が消え、モニターに新たに映し出されたのはファルケの強化スキンの設計図だった。
「この強化スキンの設計図……何者かがデプレダという魔界の組織に流出させたのは知っているな?」
ファルケの言葉にリリーとシュガーは頷く。
この強化スキンを元に、魔物が地上世界でも力を損なわない装備、凶魔スキンが生み出された。
「誰がデータを盗んだのか、俺も気になってね。色々と調べていたんだが……どうも雲行きが怪しくてね」
「どういうことですか……?」
怪訝な顔をするシュガーに、ファルケは肩を竦める。
「この開発データはいざという時のために俺がネットに隠しておいたものだ。魔界の連中が到底探し出せるものじゃない。見つけ出すのは地上世界の人間の協力が必要になるだろう」
「こっちの世界にデプレダの協力者が?」
魔界の組織であるデプレダは、地上で自由に活動出来ない制限があるため、地上の人間を使って工作活動をしていた。
国際教導学園を一時乗っ取った池岡政次という男も、政府の官僚でありながらデプレダの協力者だった。
「俺はその協力者についても突き止めた。あのデータにアクセス出来るのは世界でも一握りのハッカーだけだ。探すのはそう難しくなかったよ。だが、そこからがどうも妙な話でな……」
ファルケは椅子に座り直し、前傾姿勢になりながらシンフォニックナイツをじっと見つめた。
「しばらくそのハッカーの周囲を観察していたが、魔界の気配がまるでない。それどころか、そいつは裏で政府ともつながっているような奴だった」
「政府と……!?」
リリーが驚いたように目を見開く。
「そうだ。そしてそれだけじゃない。そのハッカーは政府を通じて、ロアの人間とも接触しているような形跡があった」
「なっ……!?」
ファルケの言わんとしているところを察し、シュガーが吃驚する。
「わかったようだな、シンフォニックシュガー。強化スキンの情報をデプレダに流したのは、ロアの人間の可能性もあるってことだ」
「そ、そんなバカな! そんなことあり得ません!」
思わず大声を上げたリリーに、ファルケは鼻を鳴らす。
「現実を見ろ。レムティアナイツの一件で裏にいたのは王宮内部の人間だったじゃないか。デプレダとつながっている奴がいたっておかしくはないだろう。そんな奴にとって、女王に近い地上の魔法戦士は邪魔な存在のはずだ」
ファルケの嘲るような物言いに、リリーは奥歯を噛む。
確かにファルケの言う通り、今は王宮内の人間でも無条件に信用できる状況ではなかった。
ファルケは背もたれに体重を預け、小馬鹿にしたような笑みをこぼす。
「敵対している魔界はもとより、今後ロアは地上世界でも良くも悪くも大きな存在になるだろう。魔物に対抗するため、魔法技術の進歩のため、あらゆる事象でロアの存在が欠かせなくなる。恐らく世界の中心となっていくだろう。そして光が強くなれば、当然影も濃くなる」
「…………」
シンフォニックナイツはファルケに何も言い返せない。ファルケの分析は正しく、そしてシンフォニックナイツも同じように考えていたからだった。
「権力欲しさに蠢き出すのは一人や二人じゃないだろう。そんな臣下どもを抑えるには、ティアナ女王は力不足だったんじゃないか?」
ファルケの言葉に、リリーが鋭い視線を向ける。
「クイーン・ティアナは懸命に国を治めています。ロアも、地上世界も平和であるために、身を捧げて働いていらっしゃるのです……!」
リリーの声に怒りにも似た迫力が滲む。
そんなリリーを探るように見ながら、ファルケは言う。
「治世の才はあっても、王となるには若すぎたんじゃないか? 前女王のグロリアに引退を撤回してもらって、戻ってきてもらった方が……」
「やめてください!」
リリーがたまりかねたように叫ぶ。
その過剰とも言える反応に、ファルケは喉の奥で小さく唸った。
「……まあ、話はここまでにしようか。あまり長居しているわけにもいかないからな。俺とシルヴァはロアの軍隊にも追われているみたいなんでね。また会おう、シンフォニックナイツ」
それだけ言うと、ファルケは転移魔法によってその場から姿を消した。
「しまった……! あらかじめ転移魔法の準備を……!」
ファルケを取り逃がし、シュガーは悔しそうに唇を噛む。
「…………」
リリーは武器を納めると、拳を握りしめて俯く。
そんなリリーにシュガーが寄り添った。
「……状況はよくありません。ですが、いつか平和が来ると信じて戦い続けましょう。私たちにできるのはそれだけなんですから」
優しく励ましてくれるシュガーに、リリーは微笑を向けた後、決意とともに表情を改めた。
「うん……私たちは負けるわけにはいかない……クイーンティアナのため……そして、もういないグロリア様のためにも……!」

