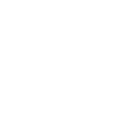
now loading...
caption
木漏れ日要らず
それはレトロな雰囲気の喫茶店だった。
看板は木製で、壁はレンガだ。もっとも、建築基準法的な問題があるので、恐らく薄く切ったレンガを壁に貼り付けてそれっぽく見せているだけであろう。
しかしそれでこの喫茶店の雰囲気が安っぽく見えるわけではない。そこまでしてレトロさを演出しようとする心意気が、逆に客足を吸い寄せる。
そんな店の古めかしい外観とは裏腹に、現代的な情報デバイスであるスマートホンの地図アプリで店の名前と位置を確認した七瀬凛々子は、ドアを開けて店内へと足を踏み入れた。
店に入ってまず目に入るのは、レジカウンターの背後にある大きな蓄音機である。年季の入り具合から、ただの装飾品ではなく実際に使われていた本物かも知れない。
外観と同じく店内もレトロな雰囲気で統一されており、懐古趣味的な小物が並べられていた。
「いらっしゃいませ」
店主だろうか、初老の男性がカウンターの中から声をかけてくる。口髭を生やした、店と同じくレトロな雰囲気を身に纏った、穏やかそうな老人だった。
「席にご案内いたしましょうか」
凛々子は首を横に振る。
「いえ、待ち合わせでして……」
その言葉が終わるよりも早く、店の奥から声がかかる。
「凛々子先輩、こっちです」
声をかけてきたのは、凛々子のよく知る女性、柚木香那葉であった。
凛々子は店主に会釈をすると、香那葉のいるテーブルに向かう。
「ごめんなさい、お待たせしました」
凛々子の座った席の対面には香那葉の他にもう一人、宮守麻由希が座っていた。
「迷ってたんですか、凛々子さん」
クスクスと笑う麻由希に、凛々子は頬を膨らませる。
「初めて来るお店だったから……もう、そんなに笑わないでよ」
「うふふ、ごめんなさい」
麻由希は謝りながら凛々子にメニュー表を差し出す。
 今日は香那葉も麻由希も仕事が休みだということで、三人でお茶でも飲もうという話になったのだった。
「凛々子先輩、お体の調子はどうですか?」
香那葉が心配そうにそう尋ねてくる。
それに対し、凛々子は曖昧な笑みを浮かべた。
「うん、体の方はもうすっかり元気」
体の方は――その言葉が意味するところを察し、香那葉と麻由希は一瞬だけ視線を交わし、それから何事もなかったかのように笑顔になった。
「元気なら安心しました! 今度ジムで一緒にトレーニングしましょう!」
麻由希が明るく言い、凛々子もつられて微笑む。
凛々子――スイートリップは、かつて繰り広げられた「ゲート」と呼ばれる、具現化した魔術演算術式に取り込まれ、この世界から消えていた。
魔法戦士の仲間の尽力によって、無事こちらの世界へサルベージされた凛々子だったが、長期間ゲートに取り込まれていた影響は、決して軽いものではなかった。
こちらの世界に帰還した後、凛々子は昏睡状態に陥り、しばらく目を覚まさなかった。
そして凛々子が眠っている間、眼帯をつけたもう一人の「スイートリップ」が出現し、魔法戦士たちを困惑させた。
その眼帯をつけたリップの正体は、甘樹菜々芭の分析によって、ゲートによって切り離された凛々子の魔力が、ゲート内で「何か」と融合して具現化したものではないかと仮説が立てられた。
しかし、それは未だに推測の域を出ない。
その騒動が落ち着くと、凛々子はようやく目を覚ます。切り離されていた魔力が戻ったことで、意識を回復したのである。
しかし、意識と魔力が戻っても、以前と同じというわけにはいかなかった――。
「それで、魔法戦士の仲間たちとは仲良くできてる?」
凛々子の質問に、香那葉と麻由希は笑顔で頷く。
「はい。皆さんとてもよくしてくれますよ」
「後輩も増えましたしね。先輩として頑張らないと!」
そんな二人に凛々子も笑みを見せた。
「魔法災害も増えてるし、魔法戦士の連携はより一層大事になってくると思うから、チームワークは大切にね」
そんな話をしている間に、注文しておいたメニューが届く。
三人はコーヒーや紅茶を飲みながら、セットで頼んだケーキを口に運ぶ。
「あ、これ美味しいです。スポンジの間にチョコクリームが挟んであって、生クリームの上からもチョコチップ……チョコの風味が際立ってますね」
ケーキを分析しながら食べている香那葉に、麻由希は苦笑をこぼす。
「休日くらい、お仕事のこと忘れたら?」
「いえ、私はまだまだ駆け出しですから。常に勉強です!」
パティシエとしての生真面目っぷりに、凛々子は笑みの浮かぶ唇で紅茶を一口飲んだ。
――香那葉も麻由希も、自分が眠っている間に立派になった。
一抹の寂しさとともに凛々子はそんなことを思う。
実際、凛々子がゲートに取り込まれている間、世の中は大きく変わっていた。
魔法が一般にも認知されるようになり、世間は新たに出現した科学とは別に新しい「力」をどう扱うべきか、まだ戸惑っている。
中には魔力を不浄なものとし、排除しようとする過激な思想もあるようだった。
それは魔法が満ちる異世界「ロア」の存在も大きく影響している。
地上以外に文明があるということは、よの人々にとって大きなショックであった。
地球の人間こそが唯一の知的生命体――その考えは程度の差はあれ誰もが持っている。
ロアはそれを根本から崩す存在であった。
故に、ロアへの忌避と反発を持つ人々は少なくない。
異文化との交流と、異文明との交流はまったく別のものだ。
異文明との接近遭遇は、歴史に刻まれている限りにおいては地上の人類にとって初めてのことである。紛糾しても致し方ないことであった。
「そう言えば、凛々子さんはこれからどうするんです? エリクシルナイツの二人みたいに国際教導学園で教師でもやるんですか?」
麻由希の問いに、凛々子は少し考えてから答える。
「まだハッキリとは決めてないけど……地上世界とロアとの間の橋渡しみたいな……そんな仕事ができたらいいかなって」
地上とロアが難しい時期だからこそ、二つの世界の間を取り持ちたい。それが今の凛々子の素直な気持ちであった。
元々、凛々子の夢は外交官であった。国と国の間の問題を解決して、少しでも平和に貢献したい――そんな風に考えていた。
そういう意味では、昔と変わらない理想を追いかけていると言ってよかった。
「凛々子先輩ならできますよ!」
香那葉は力強く断言する。
凛々子が前を向いて歩き出そうとしていることが、嬉しくて仕方ないといった様子だった。
「凛々子さんならこっちの世界の代表を任せても安心できますね」
麻由希もそんなことを言い出し、凛々子は思わず苦笑した。
と、同時に通知音が三つ鳴り響く。
三人が慌ててスマートホンを取り出すと、アプリが魔法災害の発生を知らせていた。
「香那葉ちゃん!」
「うん!」
麻由希と香那葉はほぼ同時に立ち上がる。
「凛々子先輩、私たち、行ってきます!」
スイートキッスである香那葉、スイートパッションである麻由希は、魔法戦士としての使命を果たすべく現場に向かうつもりだった。
「気をつけて、二人とも……!」
凛々子は店を飛び出していった二人を見送る。
「私も――」
その言葉は最後まで出なかった。
行けば足手まといになることは、重々承知していたからだ。
――今の凛々子は、魔法戦士ではないのだから。
凛々子は唇を噛んで、拳をギュッと握る。
ゲートに取り込まれていた間に流れた時間は、キッスとパッションを大きく成長させていた。
魔法戦士としても、人間としても。
もう、凛々子が守る必要もないくらいに。
過去を切り取ったような喫茶店の中で、凛々子はただ立ち尽くしていた――。
今日は香那葉も麻由希も仕事が休みだということで、三人でお茶でも飲もうという話になったのだった。
「凛々子先輩、お体の調子はどうですか?」
香那葉が心配そうにそう尋ねてくる。
それに対し、凛々子は曖昧な笑みを浮かべた。
「うん、体の方はもうすっかり元気」
体の方は――その言葉が意味するところを察し、香那葉と麻由希は一瞬だけ視線を交わし、それから何事もなかったかのように笑顔になった。
「元気なら安心しました! 今度ジムで一緒にトレーニングしましょう!」
麻由希が明るく言い、凛々子もつられて微笑む。
凛々子――スイートリップは、かつて繰り広げられた「ゲート」と呼ばれる、具現化した魔術演算術式に取り込まれ、この世界から消えていた。
魔法戦士の仲間の尽力によって、無事こちらの世界へサルベージされた凛々子だったが、長期間ゲートに取り込まれていた影響は、決して軽いものではなかった。
こちらの世界に帰還した後、凛々子は昏睡状態に陥り、しばらく目を覚まさなかった。
そして凛々子が眠っている間、眼帯をつけたもう一人の「スイートリップ」が出現し、魔法戦士たちを困惑させた。
その眼帯をつけたリップの正体は、甘樹菜々芭の分析によって、ゲートによって切り離された凛々子の魔力が、ゲート内で「何か」と融合して具現化したものではないかと仮説が立てられた。
しかし、それは未だに推測の域を出ない。
その騒動が落ち着くと、凛々子はようやく目を覚ます。切り離されていた魔力が戻ったことで、意識を回復したのである。
しかし、意識と魔力が戻っても、以前と同じというわけにはいかなかった――。
「それで、魔法戦士の仲間たちとは仲良くできてる?」
凛々子の質問に、香那葉と麻由希は笑顔で頷く。
「はい。皆さんとてもよくしてくれますよ」
「後輩も増えましたしね。先輩として頑張らないと!」
そんな二人に凛々子も笑みを見せた。
「魔法災害も増えてるし、魔法戦士の連携はより一層大事になってくると思うから、チームワークは大切にね」
そんな話をしている間に、注文しておいたメニューが届く。
三人はコーヒーや紅茶を飲みながら、セットで頼んだケーキを口に運ぶ。
「あ、これ美味しいです。スポンジの間にチョコクリームが挟んであって、生クリームの上からもチョコチップ……チョコの風味が際立ってますね」
ケーキを分析しながら食べている香那葉に、麻由希は苦笑をこぼす。
「休日くらい、お仕事のこと忘れたら?」
「いえ、私はまだまだ駆け出しですから。常に勉強です!」
パティシエとしての生真面目っぷりに、凛々子は笑みの浮かぶ唇で紅茶を一口飲んだ。
――香那葉も麻由希も、自分が眠っている間に立派になった。
一抹の寂しさとともに凛々子はそんなことを思う。
実際、凛々子がゲートに取り込まれている間、世の中は大きく変わっていた。
魔法が一般にも認知されるようになり、世間は新たに出現した科学とは別に新しい「力」をどう扱うべきか、まだ戸惑っている。
中には魔力を不浄なものとし、排除しようとする過激な思想もあるようだった。
それは魔法が満ちる異世界「ロア」の存在も大きく影響している。
地上以外に文明があるということは、よの人々にとって大きなショックであった。
地球の人間こそが唯一の知的生命体――その考えは程度の差はあれ誰もが持っている。
ロアはそれを根本から崩す存在であった。
故に、ロアへの忌避と反発を持つ人々は少なくない。
異文化との交流と、異文明との交流はまったく別のものだ。
異文明との接近遭遇は、歴史に刻まれている限りにおいては地上の人類にとって初めてのことである。紛糾しても致し方ないことであった。
「そう言えば、凛々子さんはこれからどうするんです? エリクシルナイツの二人みたいに国際教導学園で教師でもやるんですか?」
麻由希の問いに、凛々子は少し考えてから答える。
「まだハッキリとは決めてないけど……地上世界とロアとの間の橋渡しみたいな……そんな仕事ができたらいいかなって」
地上とロアが難しい時期だからこそ、二つの世界の間を取り持ちたい。それが今の凛々子の素直な気持ちであった。
元々、凛々子の夢は外交官であった。国と国の間の問題を解決して、少しでも平和に貢献したい――そんな風に考えていた。
そういう意味では、昔と変わらない理想を追いかけていると言ってよかった。
「凛々子先輩ならできますよ!」
香那葉は力強く断言する。
凛々子が前を向いて歩き出そうとしていることが、嬉しくて仕方ないといった様子だった。
「凛々子さんならこっちの世界の代表を任せても安心できますね」
麻由希もそんなことを言い出し、凛々子は思わず苦笑した。
と、同時に通知音が三つ鳴り響く。
三人が慌ててスマートホンを取り出すと、アプリが魔法災害の発生を知らせていた。
「香那葉ちゃん!」
「うん!」
麻由希と香那葉はほぼ同時に立ち上がる。
「凛々子先輩、私たち、行ってきます!」
スイートキッスである香那葉、スイートパッションである麻由希は、魔法戦士としての使命を果たすべく現場に向かうつもりだった。
「気をつけて、二人とも……!」
凛々子は店を飛び出していった二人を見送る。
「私も――」
その言葉は最後まで出なかった。
行けば足手まといになることは、重々承知していたからだ。
――今の凛々子は、魔法戦士ではないのだから。
凛々子は唇を噛んで、拳をギュッと握る。
ゲートに取り込まれていた間に流れた時間は、キッスとパッションを大きく成長させていた。
魔法戦士としても、人間としても。
もう、凛々子が守る必要もないくらいに。
過去を切り取ったような喫茶店の中で、凛々子はただ立ち尽くしていた――。
 今日は香那葉も麻由希も仕事が休みだということで、三人でお茶でも飲もうという話になったのだった。
「凛々子先輩、お体の調子はどうですか?」
香那葉が心配そうにそう尋ねてくる。
それに対し、凛々子は曖昧な笑みを浮かべた。
「うん、体の方はもうすっかり元気」
体の方は――その言葉が意味するところを察し、香那葉と麻由希は一瞬だけ視線を交わし、それから何事もなかったかのように笑顔になった。
「元気なら安心しました! 今度ジムで一緒にトレーニングしましょう!」
麻由希が明るく言い、凛々子もつられて微笑む。
凛々子――スイートリップは、かつて繰り広げられた「ゲート」と呼ばれる、具現化した魔術演算術式に取り込まれ、この世界から消えていた。
魔法戦士の仲間の尽力によって、無事こちらの世界へサルベージされた凛々子だったが、長期間ゲートに取り込まれていた影響は、決して軽いものではなかった。
こちらの世界に帰還した後、凛々子は昏睡状態に陥り、しばらく目を覚まさなかった。
そして凛々子が眠っている間、眼帯をつけたもう一人の「スイートリップ」が出現し、魔法戦士たちを困惑させた。
その眼帯をつけたリップの正体は、甘樹菜々芭の分析によって、ゲートによって切り離された凛々子の魔力が、ゲート内で「何か」と融合して具現化したものではないかと仮説が立てられた。
しかし、それは未だに推測の域を出ない。
その騒動が落ち着くと、凛々子はようやく目を覚ます。切り離されていた魔力が戻ったことで、意識を回復したのである。
しかし、意識と魔力が戻っても、以前と同じというわけにはいかなかった――。
「それで、魔法戦士の仲間たちとは仲良くできてる?」
凛々子の質問に、香那葉と麻由希は笑顔で頷く。
「はい。皆さんとてもよくしてくれますよ」
「後輩も増えましたしね。先輩として頑張らないと!」
そんな二人に凛々子も笑みを見せた。
「魔法災害も増えてるし、魔法戦士の連携はより一層大事になってくると思うから、チームワークは大切にね」
そんな話をしている間に、注文しておいたメニューが届く。
三人はコーヒーや紅茶を飲みながら、セットで頼んだケーキを口に運ぶ。
「あ、これ美味しいです。スポンジの間にチョコクリームが挟んであって、生クリームの上からもチョコチップ……チョコの風味が際立ってますね」
ケーキを分析しながら食べている香那葉に、麻由希は苦笑をこぼす。
「休日くらい、お仕事のこと忘れたら?」
「いえ、私はまだまだ駆け出しですから。常に勉強です!」
パティシエとしての生真面目っぷりに、凛々子は笑みの浮かぶ唇で紅茶を一口飲んだ。
――香那葉も麻由希も、自分が眠っている間に立派になった。
一抹の寂しさとともに凛々子はそんなことを思う。
実際、凛々子がゲートに取り込まれている間、世の中は大きく変わっていた。
魔法が一般にも認知されるようになり、世間は新たに出現した科学とは別に新しい「力」をどう扱うべきか、まだ戸惑っている。
中には魔力を不浄なものとし、排除しようとする過激な思想もあるようだった。
それは魔法が満ちる異世界「ロア」の存在も大きく影響している。
地上以外に文明があるということは、よの人々にとって大きなショックであった。
地球の人間こそが唯一の知的生命体――その考えは程度の差はあれ誰もが持っている。
ロアはそれを根本から崩す存在であった。
故に、ロアへの忌避と反発を持つ人々は少なくない。
異文化との交流と、異文明との交流はまったく別のものだ。
異文明との接近遭遇は、歴史に刻まれている限りにおいては地上の人類にとって初めてのことである。紛糾しても致し方ないことであった。
「そう言えば、凛々子さんはこれからどうするんです? エリクシルナイツの二人みたいに国際教導学園で教師でもやるんですか?」
麻由希の問いに、凛々子は少し考えてから答える。
「まだハッキリとは決めてないけど……地上世界とロアとの間の橋渡しみたいな……そんな仕事ができたらいいかなって」
地上とロアが難しい時期だからこそ、二つの世界の間を取り持ちたい。それが今の凛々子の素直な気持ちであった。
元々、凛々子の夢は外交官であった。国と国の間の問題を解決して、少しでも平和に貢献したい――そんな風に考えていた。
そういう意味では、昔と変わらない理想を追いかけていると言ってよかった。
「凛々子先輩ならできますよ!」
香那葉は力強く断言する。
凛々子が前を向いて歩き出そうとしていることが、嬉しくて仕方ないといった様子だった。
「凛々子さんならこっちの世界の代表を任せても安心できますね」
麻由希もそんなことを言い出し、凛々子は思わず苦笑した。
と、同時に通知音が三つ鳴り響く。
三人が慌ててスマートホンを取り出すと、アプリが魔法災害の発生を知らせていた。
「香那葉ちゃん!」
「うん!」
麻由希と香那葉はほぼ同時に立ち上がる。
「凛々子先輩、私たち、行ってきます!」
スイートキッスである香那葉、スイートパッションである麻由希は、魔法戦士としての使命を果たすべく現場に向かうつもりだった。
「気をつけて、二人とも……!」
凛々子は店を飛び出していった二人を見送る。
「私も――」
その言葉は最後まで出なかった。
行けば足手まといになることは、重々承知していたからだ。
――今の凛々子は、魔法戦士ではないのだから。
凛々子は唇を噛んで、拳をギュッと握る。
ゲートに取り込まれていた間に流れた時間は、キッスとパッションを大きく成長させていた。
魔法戦士としても、人間としても。
もう、凛々子が守る必要もないくらいに。
過去を切り取ったような喫茶店の中で、凛々子はただ立ち尽くしていた――。
今日は香那葉も麻由希も仕事が休みだということで、三人でお茶でも飲もうという話になったのだった。
「凛々子先輩、お体の調子はどうですか?」
香那葉が心配そうにそう尋ねてくる。
それに対し、凛々子は曖昧な笑みを浮かべた。
「うん、体の方はもうすっかり元気」
体の方は――その言葉が意味するところを察し、香那葉と麻由希は一瞬だけ視線を交わし、それから何事もなかったかのように笑顔になった。
「元気なら安心しました! 今度ジムで一緒にトレーニングしましょう!」
麻由希が明るく言い、凛々子もつられて微笑む。
凛々子――スイートリップは、かつて繰り広げられた「ゲート」と呼ばれる、具現化した魔術演算術式に取り込まれ、この世界から消えていた。
魔法戦士の仲間の尽力によって、無事こちらの世界へサルベージされた凛々子だったが、長期間ゲートに取り込まれていた影響は、決して軽いものではなかった。
こちらの世界に帰還した後、凛々子は昏睡状態に陥り、しばらく目を覚まさなかった。
そして凛々子が眠っている間、眼帯をつけたもう一人の「スイートリップ」が出現し、魔法戦士たちを困惑させた。
その眼帯をつけたリップの正体は、甘樹菜々芭の分析によって、ゲートによって切り離された凛々子の魔力が、ゲート内で「何か」と融合して具現化したものではないかと仮説が立てられた。
しかし、それは未だに推測の域を出ない。
その騒動が落ち着くと、凛々子はようやく目を覚ます。切り離されていた魔力が戻ったことで、意識を回復したのである。
しかし、意識と魔力が戻っても、以前と同じというわけにはいかなかった――。
「それで、魔法戦士の仲間たちとは仲良くできてる?」
凛々子の質問に、香那葉と麻由希は笑顔で頷く。
「はい。皆さんとてもよくしてくれますよ」
「後輩も増えましたしね。先輩として頑張らないと!」
そんな二人に凛々子も笑みを見せた。
「魔法災害も増えてるし、魔法戦士の連携はより一層大事になってくると思うから、チームワークは大切にね」
そんな話をしている間に、注文しておいたメニューが届く。
三人はコーヒーや紅茶を飲みながら、セットで頼んだケーキを口に運ぶ。
「あ、これ美味しいです。スポンジの間にチョコクリームが挟んであって、生クリームの上からもチョコチップ……チョコの風味が際立ってますね」
ケーキを分析しながら食べている香那葉に、麻由希は苦笑をこぼす。
「休日くらい、お仕事のこと忘れたら?」
「いえ、私はまだまだ駆け出しですから。常に勉強です!」
パティシエとしての生真面目っぷりに、凛々子は笑みの浮かぶ唇で紅茶を一口飲んだ。
――香那葉も麻由希も、自分が眠っている間に立派になった。
一抹の寂しさとともに凛々子はそんなことを思う。
実際、凛々子がゲートに取り込まれている間、世の中は大きく変わっていた。
魔法が一般にも認知されるようになり、世間は新たに出現した科学とは別に新しい「力」をどう扱うべきか、まだ戸惑っている。
中には魔力を不浄なものとし、排除しようとする過激な思想もあるようだった。
それは魔法が満ちる異世界「ロア」の存在も大きく影響している。
地上以外に文明があるということは、よの人々にとって大きなショックであった。
地球の人間こそが唯一の知的生命体――その考えは程度の差はあれ誰もが持っている。
ロアはそれを根本から崩す存在であった。
故に、ロアへの忌避と反発を持つ人々は少なくない。
異文化との交流と、異文明との交流はまったく別のものだ。
異文明との接近遭遇は、歴史に刻まれている限りにおいては地上の人類にとって初めてのことである。紛糾しても致し方ないことであった。
「そう言えば、凛々子さんはこれからどうするんです? エリクシルナイツの二人みたいに国際教導学園で教師でもやるんですか?」
麻由希の問いに、凛々子は少し考えてから答える。
「まだハッキリとは決めてないけど……地上世界とロアとの間の橋渡しみたいな……そんな仕事ができたらいいかなって」
地上とロアが難しい時期だからこそ、二つの世界の間を取り持ちたい。それが今の凛々子の素直な気持ちであった。
元々、凛々子の夢は外交官であった。国と国の間の問題を解決して、少しでも平和に貢献したい――そんな風に考えていた。
そういう意味では、昔と変わらない理想を追いかけていると言ってよかった。
「凛々子先輩ならできますよ!」
香那葉は力強く断言する。
凛々子が前を向いて歩き出そうとしていることが、嬉しくて仕方ないといった様子だった。
「凛々子さんならこっちの世界の代表を任せても安心できますね」
麻由希もそんなことを言い出し、凛々子は思わず苦笑した。
と、同時に通知音が三つ鳴り響く。
三人が慌ててスマートホンを取り出すと、アプリが魔法災害の発生を知らせていた。
「香那葉ちゃん!」
「うん!」
麻由希と香那葉はほぼ同時に立ち上がる。
「凛々子先輩、私たち、行ってきます!」
スイートキッスである香那葉、スイートパッションである麻由希は、魔法戦士としての使命を果たすべく現場に向かうつもりだった。
「気をつけて、二人とも……!」
凛々子は店を飛び出していった二人を見送る。
「私も――」
その言葉は最後まで出なかった。
行けば足手まといになることは、重々承知していたからだ。
――今の凛々子は、魔法戦士ではないのだから。
凛々子は唇を噛んで、拳をギュッと握る。
ゲートに取り込まれていた間に流れた時間は、キッスとパッションを大きく成長させていた。
魔法戦士としても、人間としても。
もう、凛々子が守る必要もないくらいに。
過去を切り取ったような喫茶店の中で、凛々子はただ立ち尽くしていた――。

